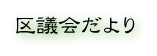【小林行男区議】
- 区民の命・健康を守るために
- 後期高齢者医療制度を白紙にもどし制度を見直すべきではないか
- 年度途中に国民健康保険に加入した区民の特定健診が受けられるように政令改正を政府に求めるとともに区として実施方策を検討すること
- 妊婦健診の負担の実態を調査し、実質無料になるように制度を充実すること
- 区民生活のセイフティーネットづくりについて
- (仮称)重度要介護高齢者への手当制度創設の検討結果を問う
- 介護保険料の低所得者への免除制度実施を求める
- 高齢者プランの見直しにあたって介護保険料値上げを抑制する国庫負担増加を求めるべき
- 「ふろわり200」の所得制限を撤廃し回数も増やすこと
- 自立支援法に基づく応益負担の廃止を政府に働きかけ合わせて区の独自軽減策の継続と負担「0」に充実すること
- 国民生活をあたためて地域経済活性化策について
- 住民生活と地域経済活性化のために個人消費、内需を喚起する経済政策が必要ではないか見解を聞く
- 区の指定管理、委託事業の賃金、労働条件を区が把握し、積算賃金を明示して確保すること。合わせて公契約条例制定を検討すること
- 商店会の街路灯電気代の補助をいっそう充実すること
- 平和事業の充実について
- 非核・平和行政として「原爆の火」の設置事業と空襲によって被災した樹木の保存の検討はその後すすんでいるか問う
- 子どもたちの広島平和ツアーなど多彩な平和行事を行うこと
- 放置自転車対策について
- 赤土小前、熊野前の自転車置き場に無料一時置き場を設置すること
- 駐輪場の完備を前提に利用料・撤去料のあり方を見直しすべき
- 西川区長は企業献金、政治資金パーテイを行わないと公約しているが変わりないか問う
《質問》
私は、日本共産党荒川区議会議員団を代表して質問を行います。
突然の福田首相の辞任表明、政権を投げ出すという無責任な態度。この一年間に安倍首相に続く異常な事態に国民の政治に対する失望と怒りは、沸騰しています。これは、これまでの小泉内閣が進めてきた「構造改革」の路線、弱肉強食の「新自由主義」の暴走がもたらした矛盾が国民生活のあらゆる分野で噴き出し、自民・公明政権の政治の行き詰まりがあらわになった事態だと考えます。
政府与党は、小泉内閣以来の「骨太方針」で、社会保障費の自然増を毎年2200億円削減する政策をすえ、年金、医療、介護、障害者、生活保護など、社会保障の分野で負担増、給付減を押し付けてきましたが、この政策の矛盾が爆発したのが後期高齢者医療制度です。
実施された4月1日以来、全国各地で「なぜ、後期高齢者を医療の中身を差別するのか」「これ以上の負担増は耐えられない」と日本列島騒然の状態が続いています。今年、75才になる人といえば、12歳という多感な時に敗戦を迎え、悲惨な空襲体験や肉親の多くを戦地で失った体験を持っている世代です。同時に戦後の国民皆保険を支えてきた世代でもあります。二十八歳の時国民皆保険制度が確立し、四十歳の時には、老人医療費が無料化されました。現役時代は、しっかり高齢者の医療を支えてきました。それがこの仕打ちです。また、現役世代にも影響を与え健保組合が負担に耐えられず、解散に追い込まれています。国民の怒りの声に押されて政府は、年金天引きの選択や減額処置の拡大など経過措置を追加すると言う小手先の手直しを行いました。荒川区でも、7月19日に保険料の納付通知が発送されて以来、7月中だけでも4200件をこす区民からの問い合わせと苦情が区役所に殺到しました。さらに、年金天引きの選択と保険料減額措置の送付と、お年寄りへの度重なる通知は、介護保険の納付通知なども含め、混乱に拍車をかけ、事務の増大を地方自治体に押し付ける結果となりました。
区長は、第二回定例会で、わが党の横山議員の質問に対して「元に戻しても解決しません」との認識を示しましたが、それは、この制度の根本的間違いに目をつぶり社会保障切り崩しを容認する態度だと言わざるを得ません。
医療改悪の集大成ともいえる後期高齢者医療制度は、何よりも医療費抑制・削減を目的としているため、75才以上という年齢によって今までの保険から切り離し、際限のない負担増を高齢者はもとより、現役世代にも求め、高齢者に差別医療を強いるものです。だからこそ、35都府県の医師会が撤廃・見直しを要求しています。後期高齢者医療制度を白紙にもどし制度を見直すべきではないでしょうか。改めて、区長の認識をお伺いします。
同時に起きている医療改悪の中で、特定健康診査が新たな制度としてはじまっています。
その中で、国保組合、健保組合などに加入していた75歳以上の方は、自分の意志とは関係なく4月1日から後期高齢者医療制度に移されました。そのため、家族は、74歳以下なら荒川区国民健康保険に転入することになります。しかし、加入日は4月2日になってしまい荒川区の健康診査が受けられなくなっています。これは、厚生労働省令でその年の4月1日現在に国民健康保険に加入している人を対象とするとし、それ以後の転入者や社会保険から離脱者は、排除してしまったからです。この人たちは、今年の10月まで行っている健診を受けることができません。こんな理不尽な事態が生まれています。
年度途中に国民健康保険に加入した区民も特定健診が受けられるように政令改正を政府に求めるとともに区として実施方策を検討することを求めます。答弁を求めます。
昨年の第2回定例会で私も質問した妊婦健診の負担軽減策は、今年度から実施し、大変歓迎されています。しかし、妊婦健診は、健康保険がきかず、自費診療であり、個々の病院、助産所などでの費用負担額の設定が異なっていたり、妊婦の個別の条件でもその頻度が異なることがあります。こうした実態を調査し、実質無料になるように制度を充実させていただきたいと思いますが、答弁を求めます。
《答弁》
【区長答弁】
後期高齢者医療制度についてのご質問にお答えいたします。
我が国の社会保障制度は、少子高齢化の進行など、社会・経済を取り巻く環境が大きく変化する中で、給付と負担のバランスや世代間・世代内の不公平を是正することなど、様々な課題に直面しております。
私は、こうした諸課題を解決し、社会保障制度の持続可能性を確保していくためには、医療・介護・福祉の分野において、サービス提供体制と費用負担のあり方などを見直しする制度改革は避けられないと考えております。
後期高齢者医療制度についても、こうした制度改革の一環として、高齢者と現役世代の負担を明確化するなど、従来の老人保健制度の問題点を改善し、我が国の国民皆保険制度を維持していく目的で実施されたものであると認識しております。
制度の発足に当たり、国の財源負担のあり方や保険料設定などに改善すべき点があったため、私は、特別区長会や広域連合協議会の場、さらには、私の持つ様々なルートを通じ、国が負担すべきものは負担し、自治体や国民の負担が過重にならないこと、また、特定の自治体に負担が偏らないことなどを強く求め、その是正を図りました。
しかし、現状においても、制度そのものやその後の国の対応などに対して、様々な意見や批判が寄せられております。私は、後期高齢者医療制度を廃止し、老人保健制度に戻しても、問題は解決しないと考えております。
最も重要な点は、自治体として本制度を運用していく中で、制度の持つ課題を発見し、その改善を図っていくことであります。区民や議員の皆様からのご意見を踏まえ、私が本部長を務める後期高齢者医療制度対策本部において、制度の内容や運用方法、周知方法等についての議論を行い、区としてできることについては積極的に取り組むとともに、持続可能な社会保障制度とするために、引き続き、国に対して、制度の不断の見直しを行うことによって、国民の理解・協力・納得が得られる仕組みにしなければならないと具申してまいります。
【福祉部長答弁】
次に特定健康診査についてのご質問にお答えいたします。
特定健康診査は、これまで老人保健法に基づいて実施してきました基本健康診査に代わる健康診査として、今年度から開始されました。各医療保険者が実施主体となり、四〇歳から七十四歳の被保険者を対象に、生活習慣病を予防するための内臓脂肪症候群に着目した健診として実施するものであります。
区においては、厚生労働省令に基づき、当該年度の四月一日における国民健康保険の加入者を対象者として実施しております。こうしたことから、転入や社会保険の離脱などの事由により、年度途中に新たに区の国民健康保険に加入された方は、この健診の対象から外れることとなります。
こうした特定健診の対象から外れた方の健診については、実施方法や実施期間等の課題を整理した上で、来年度以降はもとより、今年度の対象者につきましても、できるだけ対応する方向で検討を進めてまいります。
【健康部長答弁】
区民の命・健康を守るためにのご質問のうち、妊婦健康診査に関するお尋ねにお答えいたします。
荒川区では、母体や胎児の健康の確保と子育て支援の充実を図るため、本年四月から、妊婦健診の公費負担の回数を、昨年までの二回から十四回に大幅に拡大したところです。
そして、これまでと同じく、都内全域の医療機関で使用可能な受診券方式を採用し、その受診券に記載された標準的な健診項目については、無料で健診を受けられるようにしております。
一方、妊娠中の経過は妊婦により異なっており、妊婦健診のたびに、医師の判断により健診項目以外の検査が必要となることもあります。また、医療機関によって、検査以外の指導料として本人負担が生じることもあります。
区といたしましては、妊婦健診の公費負担のあり方につきまして、今後の国の動向を見守りながら、引き続き検討してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
《質問》
次に区民生活のセイフティーネットを保証する重点施策について伺います。
ワーキングプアーの増大など低収入・収入減、税金・保険料の負担増、物価高の三重苦が国民生活を圧迫しています。荒川区でも、国民健康保険料の滞納の増加、資格証明書の発行は、毎年1000世帯にも上ります。
新年度予算の編成や、高齢者プランの改定・介護保険の第4期計画が間じかに迫っています。本来、生活保護基準以下の収入の方から保険料を取ること自体間違っています。さらに、生活保護すら高齢者加算、母子加算などもはずすなど、憲法25条を踏みにじり、人間の尊厳をも奪いかねる事態が続いています。
今、補正予算でも、基金の積み立ては、毎年毎年増額を続け、一時的にせよ300億円にも上ろうとしています。こうした財政力を区民生活に振り向けることこそ、基礎的自治体の責務ではないでしょうか。
私の知り合いの高齢者世帯では、無年金の80代の夫婦と娘さんの三人家族、妻は要介護4でサービスの利用限度を超えて、ホームヘルプサービス、ディサービス、月一回のショートスティを利用して、他の制度を活用しても月3万数千円の利用料を支払う生活です。無年金者のこのような方でも保険料は月額4000円、二人で8000円、ここに新たに後期高齢者医療の保険料の負担増がのしかかります。これまでの蓄えの取り崩し、娘さんからの援助に頼る生活です。これでは、三人とも共倒れになりかねません。
わが党が繰り返し求めてきた。重度の介護を必要とする高齢者と支えるご家族への激励となる(仮称)重度要介護高齢者への手当ての制度。予算特別委員会では区長は検討に値すると答弁してきましたが、検討結果はどうなっているでしょうか。答弁を求めます。
また、年収120万円以下、預貯金300万円以下の方の介護保険料の免除制度の実施を求めます。
必要なサービスが提供できているか。保険料、利用料の負担は大丈夫か。特養ホームを一つ、建設すると保険料が一人当たり150円上がると想定され、また、高齢者人口が増えると保険料に跳ね返る仕組みの改善を国に求め、高齢者プランの見直しにあたって、介護保険料値上げ抑制のために国庫負担の増加を求めるべきです。答弁を求めます。
次に銭湯の入浴料も今年になって430円から450円へ値上げせざるを得なくなりました。利用者にもお風呂屋さんにとってもこの値上げは、大変なものです。だからこそ、「ふろわり200」は、高齢者のみなさんから歓迎されています。一方で銭湯を経営する方も、A重油の価格の大幅上昇などで経費がかさむ。利用客が減少する。経営そのものが成り立たなくなり、区内でも毎年毎年銭湯が一つ一つ減っていく姿を目のあたりにしています。
区民も利用回数をも考えてしまう経済状況です。「毎日お風呂で健康長生き」といきたいものです。お隣の文京区では、全区民対象に月二回100円、それに加えて、60才以上なら週一回、100円で入浴できるようにしています。荒川区も、もっと区民に利用していただいて、健康増進と交流、そして銭湯そのものの営業の安定を図るためにも、「ふろわり200」の所得制限を撤廃し、週一回にとどめないで、回数を増やしていただきたい。答弁を求めます。
障害者自立支援法ができて3年目、依然として全国の障害者団体のみなさんをはじめ、地方自治体などが応益負担に対して反対の声を上げています。障害者に一律1割の負担を求めたことがいかに障害者の働く意欲、自立を妨げるような結果になったか、一目瞭然です。荒川区も、関係者の声に押されて、3年間の経過措置として3%負担に軽減してきました。政府も低所得の負担上限額の緩和。所得の見直しなどをおこなった緊急措置を7月から実施しました。
しかし、負担をゼロに戻すことこそ、本来の姿であり、改めて国に自立支援法にもとづく応益負担の廃止をはたらきかけ、あわせて区の独自軽減策の継続と負担「0」に充実することを求めます。
《答弁》
【福祉部長答弁】
次に、重度要介護高齢者への手当制度創設についてお答えいたします。
介護保険制度には、介護サービスの利用料が負担限度額を超えた場合に払い戻される制度や、施設入所の方で所得の低い方には、所得に応じて負担限度額が設けられているなど、一定の負担軽減策があり、所得に関わらず一律に現金支給することは好ましくないと考えております。
区といたしましては、重度の高齢者といっても、状態は個々様々であり、それぞれの状況を踏まえた対応が必要であると認識しており、個別事情を汲みながら、区の様々な行政施策と連携して、区民の皆様の生活を支えていくことを基本としてまいります。
【福祉部長答弁】
次に、低所得者の介護保険料免除についてお答えいたします。
介護保険制度は、すべての国民が互いに支えあうことを理念としており、その能力に応じた負担をしていただくことが基本となっております。そのため、保険料の全額免除や保険料減免分に対する一般財源の繰入といった方法で、保険者が単独で減免することは適当ではない、とされています。また、保険料の免除ではなく制度の枠外で現金を支給することも、結果的に保険料の免除と同じで、制度の理念に反することとされています。
区では、現在、所得の最も低い段階である保険料負担第一段階、第二段階の方々にも、保険料を基準額の二分の一に減額して負担していただいております。
また、基準額の四分の三を負担いただくこととしている第三段階の方で、収入が百二十万円未満で貯蓄が六十万円未満の方について、基準額の二分の一にするという軽減策を講じております。
さらに、平成十八年度からは、標準的には六段階の保険料区分を八段階に設定することで、より能力に応じた形での保険料負担となるように努めているところでございます。
区といたしましては、今後も、このような様々な軽減策等を講じた上で、介護保険制度の理念に沿った運営に努めてまいります。
【福祉部長答弁】
次に、介護保険料値上げを抑制するため、国庫負担を増やすべきとのご質問にお答えいたします。
介護保険制度は、自助を基本としながら相互扶助によってまかなう、負担と給付の関係が明確な社会保険方式が採用されています。
介護サービスに要した費用の一割を自己負担、残る九割を給付とし、給付の二分の一を国・都・区の公費負担、二分の一を四十歳以上の全国民の保険料で充てる現行の枠組みは、その理念を反映したものであると理解しておりますが、この構成割合につきましては、介護報酬や保険料の設定とあわせて議論すべき課題であると考えております。
【福祉部長答弁】
次に、「ふろわり二〇〇」についてのご質問にお答えいたします。
区では、高齢者の健康の保持・増進や地域における区民のふれあいを促進することを目的に、満七〇歳以上を対象とする「高齢者入浴事業」を本年度から開始したところであります。幸いにして区内の高齢者のご好評を得て、既に千八百人以上の方がご利用になっているところです。
この事業では、対象者を前年度の住民税非課税者に限定しており、また、公衆浴場の利用回数を週一回としていることから、窓口等におきまして、区民から所得制限の撤廃や利用回数の見直しについての要望が寄せられております。
こうした区民の要望や区議会の意見を踏まえ、現在、所得制限のあり方や利用回数につきまして、検討を進めているところであります。
【福祉部長答弁】
次に、障害者自立支援法に関する利用者負担等のご質問にお答えいたします。
区では、障がい者が住みなれた荒川区で、安心して生活していただくために、障害者自立支援法の施行当初から、障害福祉サービス利用時の負担軽減並びに通所サービス利用における食事代の負担軽減など、全国の自治体に先駆けて荒川区独自の激変緩和策を実施してまいりました。
一方、国におきましては、十九年四月からと本年七月からの二回にわたって、障がい者や事業者の置かれている状況を踏まえ、利用者負担の見直しを行い、負担軽減策を実施したところでございます。
このような軽減策を国が実施する中、区は国の対象とならない世帯につきましても軽減の対象としており、幅広く障がい者全体の負担を軽減する制度であると認識しております。
区といたしましては、今後の法律改正と国の動向を注視しつつ、今後の軽減策を検討するとともに、必要に応じて国や東京都に対して意見・要望を伝えてまいる所存でございます。
《質問》
次に、大企業言いなりの政治は、雇用のルールを破壊し、リストラ・合理化を推進、派遣労働など規制緩和を推し進め、低賃金労働者を増大させ、外資への競争力強化といっては、大企業・大資産家には、約7兆円もの減税を推進。その結果、トヨタ自動車は、約二十年間で経常利益は2.2倍になったのに、納税額は、二割減、勤労者の給与水準は低下する一方役員報酬は引き上がり、株式配当は7.7倍となっています。大企業は空前のぼろもうけを続けたが、国民生活の実態は、実質消費支出は今年に入って一年前に比べてマイナス1.8%で四ヶ月連続前年を下回りました。実質所得はこの9年間、下降線をたどる一方です。六月の完全失業率は、4.1%、自殺者は10年連続で3万人を越えるなど、国民の苦しみは極限まで来ているのではないでしょうか。
さらに、今年に入ってから家計に重くのしかかっているのが、原油の高騰、食品の値上げ、7月の消費者物価指数は、前年同月比2.4%増と10ヶ月連続上昇・約16年ぶりの高水準になっており、九月に入っても、この間、上がり続けてきた食料品に加え、自動車や冷蔵庫など耐久消費財にも波及ししてきています。
区内でも、ある運送会社の方にお話を聞いたところ、ガソリン代の値上げの影響はひどいものだが、それ以前に「物が動かなくなっている」どの業種でも深刻な事態になっていることを感じるといっていました。
飲食店でも、ラードの食材費など高騰を続け、しかし価格には反映できない。持ち出しが続く。また商店会の衰退も深刻であります日ここ数年、商店会のシャッター通りから商店会そのものがなくなるという事態に、店舗がなくなり、そこにマンションの建設、コインパーキングになるなど、従来の会員が減り、大手チェーン店など入会しないなど、会費納入の減少などで独自の運営にも支障を来す事態になりつつあります。
現に荒川区の小売店を見ても、一九九九年に二千四百七十九軒、従業員数で一万八千七百二十三人だったものが、二〇〇七年には千八百六十八軒、従業員数一万五千八百六十五人と大幅に減っております。住民生活と地域経済活性化のために個人消費、内需を喚起する経済政策が必要ではないでしょうか。区長の見解を求めます。
わが党は、貧困の根源に、非正規雇用が労働者全体の三分の一、若者では、二分の一を占めるといった雇用のルール破壊があることを告発し、人間らしく働ける労働のルールをつくるために努力してきた。全国の労働者のたたかいの中で、政府与党も「日雇い派遣の原則禁止」の法案も準備するという規制緩和から規制強化へ「潮目の変化」を生んでいます。しかし、期間社員、請負など使い捨て雇用の問題は残されたままです。正規社員化を進めていくことが必要です。日本経済の安定のうえでも内需を拡大していく上でも重要だと考えます。
官製ワーキングプアーという言葉も生まれ、荒川区の事業に係わる雇用のあり方も問われています。
この間、荒川区は、高齢者・障害者・保育をはじめ多くの事業に対して、指定管理者制度の導入や民間委託を進めてきました。事業を任された指定管理の民間事業所、民間会社では時給900円程度のパート、アルバイト対応が増えており、毎週のように募集広告が繰り返し掲載されています。また、再委託なども当たり前のように行われています。また、区役所本体でもいまや非常勤は、比率は全職員の4割程度にまで及んでいます。
地方自治体が直接責任を持つ仕事の周りからも労働実態をしっかり点検、見直すことが重要になっています。
区の指定管理、委託事業の賃金、労働条件を区が把握し、積算賃金を明示して確保すること。合わせて。公契約条例の制定を検討することを求めます。
商店会は、地域の顔、地域社会を支えてきた、そしてこれからも下町荒川の人情をはぐくむ大切な社会資源であることは間違いありません。自主事業を支援することはもちろんのこと。負担の軽減をさらにひろげるために、今年に続き、商店会の街路灯電気代の補助をいっそう充実させることを求めたい。答弁を求めます。
《答弁》
【産業経済部長答弁】
住民生活と地域経済活性化のために個人消費、内需を喚起する経済政策が必要ではないかとのご質問にお答えします。
国内の景気回復力が弱い中で、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界経済の成長鈍化と世界的な資源・食料価格の高騰の影響を正面から受け、日本経済は厳しい局面に立たされています。このような局面に到ったのは、今般の景気拡大が外需主導によるものであったことも一因であるとの指摘がなされています。
国内景気の回復のためには、こうした世界全体の構造的な価格体系の変化に対して、生産・需要サイド双方における適切な対応を進め、内需主導による足腰のしっかりとした新たな経済成長へと結びつけていくことが重要であろうと考えております。
このようなことから、ご質問の個人消費、内需を喚起する経済政策に関しては、国レベルでの迅速かつ的確な対応が図られることが必要であると認識しております。
政府においては、先般、物価高や原油高への対応を柱とした総額十一兆七千億円規模の総合経済対策を決定したところであり、東京都においても、中小企業支援や雇用対策、新型インフルエンザ対策などを盛り込んだ九百三十五億円の大型補正予算案を発表したところです。
また、荒川区においては、七月十五日から「原油・原材料高緊急対策融資」を実施し、これまで約二百三十事業者に対し十億円超の融資斡旋を行っています。
区としましては、景気の先行きが不透明であることから、景気動向を注視しつつ、国、東京都などの対策と連携をとり、引き続ききめ細かな支援を実施して参りたいと考えております。
【管理部長答弁】
区の指定管理事業や委託事業における賃金や労働条件の確保に関するご質問にお答えいたします。
指定管理制度や事業委託の導入については、民間事業者の多様な事業経験やノウハウを活用することにより、効率的で良好な区民サービスの提供を図ることを目的としております。
区といたしましては、区の指定管理事業や委託事業の従事者はもとより、全ての労働者が最低賃金法や労働基準法等に基づく適正な雇用条件の下で仕事を行うことは重要なことであると認識しております。
同時に、区による賃金や雇用条件の義務付けは、事業活動を必要以上に制約し、指定管理制度や事業委託の効果を損なう恐れもあり、難しいものと考えております。
また、公契約条例の制定につきましては、これまで委員会審議の際にもお答え申し上げましたように、公契約に係わる特定の労働者のみを対象とした賃金保障等を行うことの是非や、現在の法体系の下で、区としてどこまで実効ある条例の制定や制度の構築ができるのか、未だ整理すべき課題が多いものと考えております。
区といたしましては、今後とも適正な発注価格の設定や法令遵守の指導を行うとともに、受託事業者による履行状況を把握し、法令や契約に従った良好な履行が確保されるよう、対応を図ってまいりますので、ご理解をお願いいたします。
【土木部長答弁】
商店会街路灯についてのご質問にお答えします。
商店会街路灯の電気代補助につきましては、昨年までの四分の一の補助から、商店会の街路灯が、まちの暗がり対策としても貢献していることを考慮し、今年度より、四分の三に増額をしたところでございます。
今回の補助金の増額につきましては、商店街連合会の理事会等でもご説明し、各商店会から喜ばれておりますので、このまま継続してまいります。
《質問》
本日は7年前、世界を震撼させた卑劣な9.11同時多発テロが起た日であります。そして、このことを口実としたアメリカの無法な報復戦争は、今でもアフガニスタン、イラクで憎しみを広げ、テロと暴力の悪循環が深刻化する悲惨な状況が続いています。先日もアフガニスタンへの農業支援のNGOの日本人青年が殺害されるという痛ましい事件が起きました。
戦争は、テロと暴力の土壌をひろげるだけです。テロの温床となっている貧困などの問題に対して有効に対処できる平和的手段でこそ解決の道が開けます。
また、世界の脅威になっている核兵器をめぐる動きは、アメリカのシュルツ元国務長官などアメリカ政府の中枢にいた4氏が核兵器廃絶を呼び掛けるようになったり、被爆地・広島・長崎市長が提唱する「平和市長会議」は130カ国2317都市、国内132県、市、町、村加盟するに至っています。広島市長は「核兵器から市民を守るには核兵器廃絶しかないというのが心理だ」と言います。私もそう思います。
荒川区は1995年に「平和宣言」を行いました。平和であり続けるためには「平和の尊さ」を繰り返し実感する取り組み、平和市長会議が提唱する核兵器廃絶へのアピールなどの意思表明など粘り強い取り組みが必要です。区のこの間の取り組みを見ますと8月15日正午の黙祷の実施など、継続して意識化されているものは、評価できるものの、年々弱まってきているのではないかと感じます。風化をさせてはなりません。
東京空襲の初被弾地になった荒川区、戦争体験、被爆の実相を直接語りつなげるのも、わずかな時間になりつつあります。ふさわしい住民参加の平和事業を計画したらどうでしょうか。
わが党がこれまで提案してきた非核・平和行政として「原爆の火」の設置や空爆によって被災した樹木の保存の検討はその後、進んでいるのでしょうか。お答えください。
また、子どもたちの広島平和ツアーなど多彩な平和事業をおこなうこと。答弁を求めます。
《答弁》
【総務企画部長答弁】
平和事業に関するご質問にお答えいたします。
荒川区は、戦後五十年にあたる平成七年に、人類の幸福と世界の恒久平和を願って、「荒川区平和都市宣言」を行いました。
また、区民向けの講演と映画の集い、学童疎開や東京大空襲の経験者による小学校での講演、ふるさと文化館や図書館での平和関連展示等の平和事業を実施してまいりました。
ご提案をいただいた福岡県星野村で守り続けてきた「原爆の種火」をはじめとする「原爆の火」、戦争を生き延びた被災樹木の保存、子どもたちの平和ツアーについては、それぞれ平和について理解を深める上で有意義な素材であり、今後も調査・検討を続けてまいります。
区といたしましては、平和への取組みの重要性は十分に認識しているところであり、「荒川区平和都市宣言」の理念に沿ってこれからも区民とともに、平和を願い、平和を育んでまいる所存でございます。
《質問》
次に放置自転車対策についてお伺いします。
毎年多額な費用が費やされてもなかなか改善されないのが現状ではないでしょうか。私どもが視察した中央区では、1999年に有料化に向けて検討した際、荒川区も含め、アンケート調査を行い、「駐輪場の利用が促進されない」「放置自転車が減少しない」「撤去・保管費用が大変」などデメリットが多いことを考えると無料を継続して街をきれいにするという行政責任を果たそうという結論になったそうです。
区の役割と区民の協力が信頼と協力の関係を創っていかなければ、解決への道は開けません。
日暮里駅前の地下駐車場への誘導はまだまだ努力が要るようです。新たに設置された日暮里・舎人ライナーの「赤土小駅」「熊野前駅」に設置した自転車置き場も予想以上に利用が少なく、空きスペースを大きく残したままとなっています。一方、一時的には利用したくても登録制になっているため、空いているのにもかかわらず、利用できず、結果として放置自転車になっているケースも見受けられます。利用されてこそ、自転車駐輪場の役割が発揮されます。
そこで、赤土小前、熊野前の自転車置き場に無料一時置き場を設置することを求めます。答弁を求めます。
懲罰的な撤去料5000円や高い利用料金を駐輪場の完備を前提に利用料・撤去料のあり方を見直しすべきと考えますがいかがでしょうか。答弁を求めます。
最後に区長の政治姿勢について改めてお伺いします。
4年前、前区長の贈収賄事件とその辞任によって行われた区長選で、西川区長は、企業団体の献金を受け取らない。政治資金パーティーなど開催を行わないことを公約してきました。
側聞するところ去る9月4日、1万円会費「出版記念パーティー」が盛大に開催されたと伺いました。選挙を目前のこの時期のことですから、改めて、企業団体からの献金を受け取らないこと。政治資金パーティーを行わないことに変わりはないか伺います。
答弁を求めます。
これで私の第一回も質問は終わります。
《答弁》
【土木担当部長答弁】
まず、赤土小学校駅、熊野前駅の各自転車置場に無料の一時利用自転車置場を設置すべきとのご質問に、お答えいたします。
日暮里・舎人ライナーの開通に伴い、設置いたしました、両自転車置場につきましては、今日までの利用状況は、当初の利用想定より、利用率が低い状況となっておりますが、両自転車置場ともに、設置してから五ヶ月と、間もないため、今後の利用者の推移を見ながら、その有効利用について、検討する必要性があると、認識しております。
区といたしましては、今後とも、PR活動を積極的に実施し、利用者の増大に努めてまいりたいと考えております。
続きまして、利用料・撤去料のあり方についてのご質問に、お答えいたします。
まず、現在の駐輪施設の整備状況ですが、新三河島駅、三ノ輪駅周辺につきましては、区の駐輪施設が設置されておりません。
また、町屋駅では、センターまちや自転車駐車場が、日によっては、満車状態となっている状況から、鉄道事業者・民間等に駐輪施設設置の協力を求めるなど、駐輪場の整備に取組んでいるところであります。
したがいまして、利用料・撤去料の見直しについて、今、直ちに、改定する時期にはないものと考えておりますが、区内の駐輪施設が十分に整備された際には、検討することも必要と考えております。
▲ページトップ
|