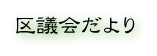�y�����a�j��c�z
- �t�i���̍�������ő��łɂ��ċ撷�̔F����₤�B
- ���̎s�ꌴ���ƋK���ɘa����斯�̂��炵�ƒn����������邽�߂�
- ���ی����ɂ��ẮA�Ꮚ���҂ւ̖Ə����x��n�݂��邱�ƁB
- �q��Đ���̉ƒ��⏕�ɂ��Č������J�n���邱�ƁB
- ��Q�ҕ����T�[�r�X�R�����S���Ȃ������ƁB
- �����A�p���ٗp�͐��K�őΉ����邱�ƁB
- ��̎w��Ǘ��҂ɂ��āA���������������s���A�斯�T�[�r�X��J�������Ȃǂ̎��Ԃ𖾂炩�ɂ��āA�K�v�ȑ���u���邱�ƁB
- �s�A��̗v�j�ᔽ���J��Ԃ����u�����ۈ牀�v�̎��ƌp���ɑ��錵���ȏ��u�ƕۈ�̉��P��₤�B
- ����ۈ牀�̎��̊m�ۂɋ旧�E�Љ���@�l���̋��͑̐������邱�ƁB
- 6���̕ۈ牀���H�������Ԉϑ��͒��~���邱�ƁB
- ���闢�E�O�͓��̊X�Â���ɂ���
- ���闢�w�O�ĊJ���̋��P���O�͓��w��k�̍ĊJ���v��ɂǂ��������̂��B��̌�����₤�B
- ����B�a�������ɁA���f������ݒu���AJR�\���ɎԃC�X�Ή��ł���X���[�v�t���̊K�i��ݒu���邱�ƁB�܂������w�ɉ����ɍ��킹������ݒu�AJR���闢�w����ɂ�����u���݂����v�̃o���A�t���[�����s�����ƁB
- �����^�]���Ă��鋞�l���k���ɂ��āA��Ƃ��ē��闢�w��Ԃ�JR�ɓ��������邱�ƁB
- JR�O�͓��w�ɁA�G���x�[�^�[�Ɖ���G�X�J���[�^�[�𑁊��ɐݒu����悤JR�ɓ��������邱�ƁB
- ���̌������ƕ⏕���������āA�����Z��݂̎��ƕ⏕�ɐ肩���邱�Ƃɂ��āB
- ����{��[���ɂ���
- �u�K�n�x�ʊw�K�v��S�ʓI�Ȍ����s���A�w�Z����̔��f�ŁA���l�Ȋw�K�w�����@�����{�ł���悤���������s�����ƁB
- ���w�Z�̒�A���w�N�̉p��Ȃ̒��~�ɂ���
- �u�����w�Z�Z�ɐ����v��v�̍���ɂ������ẮA�w�Z�I�𐧂̌������Ə��l���̊w���Ґ�������ɓ��ꂽ�v��ɂ��邱�ƁB
�s����t
�@���́A���{���Y�}��c�c���\����4���ڂ̎����v���܂��B���ɁA����ő��Ŗ��ɂ��Ăł���܂��B
�@���c�́A�u�Љ�ۏፑ����c�v�������ĔN���A��ÂȂǎЉ�ۏ�S�ʂɂ��āA���t�ƕ��S�̂�����̋c�_���s�����ƁB���킹�āA��b�N���̍��ɕ��S���グ�̂��߂ɏ���ő��łɓ��ݍ����_���H�܂łɏo���A09�N�x�ȍ~�ɏ���ő��ł����s�Ɉڂ��Ƃ��Ă��܂��B
�@ �܂��A�n���@�l���ʐł̑n�݂ɂ���ē����s�∤�m���Ȃǂ���S�牭�~���܂�̖@�l���Ɛł𑼎����̂ɏ��^�����邱�Ƃ����߂܂����B
�@ �n���ւ̔��{�I�Ō��Ϗ����s�킸�ɒn����t�ł��팸���A�@�l�ېł̓s�s�Ԃ݂̕����P���Ȃ��܂܁A�n�������𐭕{���U�蕪����d�g�݂́A���܂�ɗ��\�ł���܂��B�������^�}�Ő���j�ł́A���̑[�u������ő��ł܂ł̎b��[�u���Ƃ��āA����Βn�������̂ɏ���ő��ł𔗂�e�R�ɂ�����̂ŁA�n���������W�̋�����������@���Ǝv���܂��B
�@����撷�́A����ł��ړI�łƂ��ׂ��Ƃ��˂Ă���咣����Ă��܂��B�������A����ł́A�H��ȂǓ��퐶����܂Őŋ����������҂ւ̒ɂ݂̐ŋ��ł��B
�@����œ��������炱��܂ŁA����ҁE���������Q�O�O���~�߂�����������҂̂��߂Ƃ����Ȃ���A���ۂ́A�@�l�ŗ����������̑��ƌ��ł̌����߂ɑ唼����������Ă��܂��B�������O�I�����ɒ藦���ł̔p�~��N���ېŋ����Ŋ�b�N���̍��ɕ��S�������グ���s���ƌ������^�}�̌���͎��ꂸ�A������2��8�牭�~�̕��S���A�Љ�ۏ�\�Z�ɉ�����ƌ�����̂́A6800���~��4����1�ł���܂��B
�@���c���t�́A������܂��A�N���̍��ɕ��S�����グ������ő��ł̗��R�ɂ��Ă��܂����A���̌���͂��łɎ�������Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł���܂��B
�@����撷�A�\�����v�ɂ��n���Ɗi���̊g��A�������i�̍����A�����l�グ�ȂǁA��i�ƌ������Ȃ�斯�����ɗ^����e���A����ɒn���������W�̏���ŗ����グ�Ȃǎ����̂̒��Ƃ��ėe�F�ł��Ȃ��Ǝv���܂����A���߂Đ���撷�̌������f�����܂��B
�s���فt
�y���撷���فz
�@����łɊւ��鎿��ɂ��Ă������������܂��B
�@����ł́A�Љ�ۏ���n�߂Ƃ�����I�T�[�r�X�̔�p�������鐢�オ�L�������ɕ��S���������łƂ��āA�������N�ɓ������ꂽ���̂ł��B���݁A���Ŏ����̖���߂Ă���A����I�Ȋ�ł̈�Ƃ��āA�Љ�ۏዋ�t�̑����������܂�钆�A�܂��܂��d�v������Ă���܂��B
�@����܂Őŗ�������n������ł̑n�ݓ����X�̉������s���Ă����ق��A���x�S�ʂɂ��ėl�X�ȋc�_���Ȃ���Ă��܂����B��N�\�ꌎ�̐��{�Ő�������̓��\�w���{�I�ȐŐ����v�Ɍ�������{�I�l�����x�ɂ����ẮA�g�r�y�ѐŗ��ɂ��āA�u�Љ�ۏ�����Ƃ��Ă̈ʒu�t������薾�m�ɂ���ƂƂ��ɁA��������ɕ��S��摗�肷��̂ł͂Ȃ��A����ŗ��̈��グ�ɂ���Ęd�����Ƃ��I�����̈�Ƃ��ĕ��L���������ׂ��v�Ƃ��A�܂��A�����ɑ���t�i���ɂ��ẮA�u��Ŗڂ����łȂ��A���Ŗڂ�Љ�ی����A����ɂ͎Љ�ۏዋ�t���̎�v�S�̂��l�����ׂ��v�Ƃ��Ă���܂��B��N�\�Ɋt�c���肳�ꂽ�w������\�N�x�\�Z�Ґ��̊�{���j�x�ɂ����Ă��A�u�O�ꂵ���Ώo���v���ƍ��킹�āA����ł��܂ސő̌n�̔��{�I���v�̎����Ɍ����Ď��g�ށv���ƂƂ��Ă���A����A�����\�ȎЉ�ۏ�V�X�e���̊m���̂��߂̍����Ƃ��āA�{�i�I�ȋc�_���\�肳��Ă���܂��B
�@��Ƃ������܂��ẮA�斯�̊F�l�̕��S�ɒ���������ł���Ɠ����ɁA��̍����╟���{�����ɂ��傫�ȉe��������̂ł������܂��̂ŁA����Ƃ����ɂ�����_�c�𒍎����Ă܂��肽���ƍl���Ă���܂��B
�s����t
�@���ɁA�V�N�x�\�Z�̊�{�p���Ƌ斯�����ɉ�����\�Z�̊�{�p���ɂ��Ăł���܂��B
�@�V�N�x��ʉ�v�\�Z�́A���z802���~��3�N�A��800���~���Ă��܂��B�Z���ŗ��̃t���b�g���ŋ斯��17���~�̑��A�@�l2�ł�������2�N�A��40���~�̌J��z���ŁA�����07�N�x��249���~�A����A��̋N�c��08�N�x����250���~���x�Ɉ��k����錩���݂ł��B���̋�̍����͂��A�斯�����D��Ɋ��p���ׂ��Ƃ��ł���܂��B
�@���łƕ��S���ɉ������@�}�l�[�ɂ�錴�����i�ƍ����̒l�グ�ɂ��e���́A�[���ł��B��N�P�O���ɏ����̔���n�����i���P�O���l�グ�A�p���A�˗ނȂǐH���i�̒l�グ���������܂����B���{�́A����ɍ��N�S�����珬���R�O���l�グ�����߁A�����́A���ۉ��i�ɘA�������悤�Ƃ��Ă��܂��B
�@�������i�㏸�̉e���ŁA�K�\������v���X�`�b�N���l�グ�A�A�����Đ����K���i�̒l�オ����i��ł��܂��B�܂��A�Ƃ����낱���������Ƃ���o�C�I�R���̎��v�g����āA�ƒ{�����̒l�グ���i�݁A���_���[���ł����A�C�O�ō�t�ʐς��������哤���i���オ���Ă��܂��B
�@���̐����E���ƁA������������́A�哤�����ƕ�ނ̒l�グ�ŗ��������܂��Ă�����̂́A�l�グ�ɓ��ݐ�邩�ǂ����H�v�Ă̂��ǂ���A�L�����r�[�����Q������l�グ���܂������A�s�����̎�������ɂ́A�u�����̊ԁA�]���̒l�i�Ŕ̔����܂��B�v�ƒ��莆���o�Ă��܂��B�삯���݂Œl�グ�O�̍ɂ�������A����ł����A�ꎞ�̂��Ƃł��B
�@�n��̏��X���Ǝ҂��A���ޗ����ޒl�グ�̗��̂Ȃ��ŏ���҂ɓ]�łł����A�K�}�������ĉ��i���ێ����Ă��邱�ƁA��������������ɔ������āA����̐g������ĉ䖝���Ă���ł��B
�@���ǂ������N�����{�����斯�A���P�[�g�ł��u�����Ƃł����A�P���������Ȃǂŋꂵ���v�u���������������C��H�����䖝�v�ȂNj斯�����̎��Ԃ����m�Ɍ���Ă��܂��B�\�Z�ψ����ʂ��ċc�_�����Ă����܂����A���̂悤�ȂƂ��ɁA�斯�����ɉ����ł��邩��^���Ɍ������Ă������������Ǝv���̂ł��B
�@�V�N�x�\�Z�ł́A�����c�t���S���łR�Ύ��ۈ���{�Ɠ������������A�D�w���f�̂P�S��̖������E�ۈ牀�Ȃǂ̑�O�q�ȍ~�̖������Ȃǎq��Ďx�����荞�܂�܂����B�A�w�����̊�ɘa�A��Q�҃O���[�v�z�[����A�J�x���A�V�O�ˈȏ�Ŕ�ېł̍���҂ɏT���ł������z�����̎��{�Ȃǂ�]��������̂ł���܂�
�@�������A�����̊�{���x���������߂����̂ł��B�����Ŏf���܂��B
�@���ɁA�Œᐶ����ȉ��̏����ł��������Ă�����ی������N������V������Ă��܂����A����ɍ��N10�������65�Έȏ�̍��ۗ��ƌ������҂̈�Õی������V������܂��B�����ɕ����̒l�オ��ł��B�����ی����x���邢�͈ȉ��̎����̍���҂̉��ی����͖Ə����ׂ��ł��B���߂āA�N��120���~�ȉ��ŗa����300���~�����荞��ŕs���Ȑ���������Ă��鍂��҂̉��ی����Ə��̌��������߂܂��B�������������B
�@���ɁA�q��Đ���E���������̋斯�ł������E�ۈ��E�Z���̕��S���d���Ȃ��Ă��܂��B�q��Ďx�������Ƃ��Ĉ��i�߂Ă����_�͕]�����܂����A�����ɐ�߂�Z���̓K���ȕ��S�u�ڂ����v���������A�ƒ��⏕���x�̂�����̌��������߂���̂ł���܂��B�@���S���ďZ�݁A�q��Ăł���搭��ڎw��������߂܂��B��̌��������f�����܂��B
�@��O�ɁA��Q�Ҏ����x���@�̉��v���S�̉��������ׂ��ł��B�V�N�x�����Q�҂̏��K�͍�Ə������J�����@���{�݂Ɉڍs���܂��B�����2011�N�x���ɂ͂��ׂĂ̎{�݂��ڍs�𔗂��Ă��܂��B�����x���@�̗��p�ҕ��S���������邱�ƁA����܂ł̓����s�̕⏕�͂ǂ��Ȃ�̂��H�@�{�݂̉^�c�ɂ������ĕs���ȑI�������߂��Ă��܂��B
�@�����邽�߂ɕK�v�ȏ�Q�҂̕��̕s���ȕ����T�[�r�X�����́A���v���S�Ȃ̂ł��傤���A���̖@���͕��S���ʂɂ킽�镉�S�������炵�Ă��܂��B�悪�Ǝ��ɕ��S���R���Ɍy�����������_�����āA�u���v���S�Ȃ��v�����f���ĕs�����������邱�Ƃ��ēx���߂܂��B
�@���ɁA�\�����v�H���̂��Ƃŋ斯�T�[�r�X�ቺ�������炵�Ă���搭�ւ̕s����ٗp��s�ꌴ�������̉e���ɂ��Ăł���܂��B
�@���{���������Ă����\�����v�́A��{�݂̎w��Ǘ��Ґ��x�̓����ɂ��`�F�b�N�@�\�ቺ�A�c���D��ŕۈ�̎��̒ቺ�A�p���I�ȋƖ��܂Ŕ��ΐE�����A�h���J������ɂ��T�[�r�X�̒ቺ�������N�����Ă���A����Ɏ����̎��ӂɂ��g�債�Ă��܂��B
�@����ɐ��{�́A�n���������S���@�̎{�s�ȂǁA��ԈႤ�Ɠ��ʉ�v���Ɖ�v��Ɨ��̎Z�Ƃ��āA�Ԏ��̎��Ƃ͐�̂Ă邩�A���I�ȏZ���̕��S�������߂邱�ƂɂȂ肩�˂��A����E�ۈ�E���E��ÂȂǂ̕���܂Ŏ����E�ݏ��ɍς܂��āA�s�ꌴ���ɂ䂾�˂闬���傫�������˂܂���B����ł́A�����̂̂���ׂ�������������܂��B
�@�����ŁA���ɔ��ΐE���̑���ɂ��Ďf���܂��B
�@�{���A���K�E���̕⊮�I�ȒZ���ٗp�����ΐE���ł����A����́A���K�Ɠ���J���Ŕ����E�p�����Ă���E��܂Ő��K����K�ɒu�������Ă��܂��B���Ԉȏ�Ɏ����̘J���ł��������Ȃ��Ă��܂��B�r���̐��K�E���P�U�O�O�l�ɑ��čČٗp�E�ĔC�p���܂߂����ΐE���ƗՎ��E�������킹���K�ٗp�͍��v��P�O�O�O�l�ƂR�Q�̊����ɂ܂ŋy��ł���A�h���A�ϑ��A�w��Ǘ����l����ƔK�ٗp�̔�d�͂���ɍ��܂�܂��B
�@�w�Z���H�ł͂P�Q�N�Ԃ����Όp���ٗp�̕��A�}���قł��X�N�̕������܂��B��́A���ΐE���Ɏ�C�N���X�A�����W�����Ȃǂƒ����ݒ���s���܂������A������́A�p���I�ٗp�Ɣ��f�����ꍇ�͔��̔C�p�����E����Ǝw�E����Ă��܂��B�m���ɖ{����ΐE����z�u���ׂ��E��Ŕ��̑ҋ����ꕔ���P�����ɂ��Ă����E������܂��B�����I�Ɍp������J���ɂ��ẮA���K�̗p�����邱�Ƃ��{���̖@�̐��_�ł��B������ɘa���Ă����\�����v������ɂ���܂����A�����̂Ƃ��Ă���ȏ�̕s����E������ٗp�̊g��������߂铹����]�����ׂ��ł͂Ȃ��ł��傤���B��̌��������f�����܂��B
�@���ɁA�w��Ǘ��Ґ��x�̌������ƈ�ē_���ɂ��Ăł���܂��B
���̎{�݊Ǘ��ɂ��Ė@�����肳��A���Ƃ��̂��̂��܂߂Ď{�݊Ǘ����ϑ�����w��Ǘ��Ґ��x�����{����܂����B
�@�ۈ玖�ƂȂǖ{���A�c���ɂȂ��܂Ȃ�����ɂ��c����Ƃ̎Q�����n�܂�A���܂��܂Ȗ�肪�������Ă���A���̎��ԂƐ�����Ă��܂��B
�@�����X�|�[�c�Z���^�[�ł́A�O�H�d�@�r���e�N�m�T�[�r�X�ɂ�鋤���̂��w��Ǘ��҂ɂȂ�܂������A���ۂ́A�q��Ђ̕H�T�E�r���E�F�A�Ɋۓ�������A����Ɏ{�݊Ǘ��Ɩ��ӔC�҂̂ЂƂ�́A�r���e�N�m�̐����𒅂Ȃ���A�j�Ђ���h�����ꂽ�E�����Ζ����Ă����悤�ł���܂��B�ۓ����ɓ�d�h���ł͂Ȃ����A�Ƒ������ψ���Ŏw�E�����ۂɁA�����͖���F������Ɠ��ق��Ȃ���A���̌�́A�傫�Ȗ��Ȃ��Ƃ��Ă��܂��B�O����撷�̑����d�̍��V�������ďo����������搭�ł����A�O�撷�ߕ߂̕���ɂȂ��������X�|�[�c�Z���^�[�̂��̌�̎w��Ǘ��̋���ᔽ�ɂ��Ă��A���������ȓ_������p�������@���Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@�����ȋ搭���s������܂��B�܂��A���̌��Ɖ��P����撷�擪�Ɏ����ׂ��ł͂Ȃ��ł��傤���B�w��Ǘ��Ґ��x�̂��ƂŁA�J���@�K��J���ҕ���������Ă���̂��A���肪����Ă���̂��A���_��o���A���_�����s���ׂ��ł���܂��B�������f���܂��B
�@��O�ɁA�c����Ƃ̎Q���ŁA�Ƃ�킯�[���Ȏ��ԂɂȂ��Ă���ۈ牀�̖��ł���܂��B
�@������Г��{�ۈ�x������^�c����F�ؕۈ牀�u�����ۈ牀�v�̖����J��Ԃ��w�E���Ă��܂������A��̕⏕���v�j�Ɉᔽ���ĉ������ɕK�v�ȐE�����z�u���ꂸ�A�����������ɕs�݁A�������̎��i�̂Ȃ��ۈ�m�ɒ���������ȂǓ����s����ٗ�̕����w�����Ă܂����B��́A���ʂP�Q���E1���̕⏕�����~�����悤�ł����A�F�̍Œ���̕ۈ�m�z�u�����E���A�q�ǂ������̈��S�m�ۂɔ����Ă������Ǝ҂ɁA���s���ꂽ�⏕���̏��u�������ɍs���Ȃ��Ƃ�����A�ӔC�͏d��ł��B���c���ɑ傫�Ȏ��̂��N���Ă���ł͒x���̂ł��B����̕ۈ�t����̐��ۂ̂����ɂ���邾���ł����͂��͂���܂���B�����ۈ牀�̎��Ǝ҂ւ̌����ȏ��u�ƌ��ɕۈ炳��Ă���q�ǂ������ւ̕ۈ�̉��P�ɂ��Ăǂ̂悤�ɑΏ����A���܂̔F���͂ǂ��Ȃ̂���̌��������f�����܂��B
�@����A���Z�ۈ牀�̌��đւ��ȂǂɂƂ��Ȃ��A�w��Ǘ��҂̓������\�z����܂����E�c����Ƃւ̐V���ϑ��́A���̂悤�Ȏ��Ԃ̂��ƂŔ�����ׂ��ł���܂��B
�@�����ۈ牀�ȊO�ɂ��A�F�ۈ牀���^�c���銔����Ђ��ǂ��̐X�ł�2006�N�ɉ������Ɍ��������ۈ�m���z�u����Ă��Ȃ��������Ƃ��A�s���當���w������Ă��܂��B�r���̕ۈ���x����F�E���F�A�����A�c�ۂ̕ʂ��킸�A����̕ۈ�́u���v��S�ۂ��邽�߂̋�����Ǝ҂̋��͂����邱�Ƃ��K�v�ł���Ǝv���܂��B
�@�ۈ牀�^�c�͔F�旧���̐ݗ����ŗD��Ƃ��A�w��Ǘ��҉���F�ؕۈ牀�Ȃǂ̎Q���ɂ������ẮA����Љ���@�l�̉^�c��D�悷�邱�ƁA�܂��A����ŕۈ玖�Ƃ��c�����Ƃ��鎖�Ǝ҂́A�r�������Љ���@�l���s���r���̕ۈ�̎���S�ۂ�����g�݂ɋ��͂������Ƃ��Ă͂ǂ��ł��傤���B��̌��������f�����܂��B
�@���ɁA�r���́A�ۈ牀���H�̖��Ԉϑ��ɂ�������������Ήh�{�m���z�u���Ă��P��650���~�̏���Ƃ��Ă��܂������A���D�́A�K�v�Ȍo���҂��W�߂��ꂸ�A�o���҂��m�ۂ���A�l���������A���ۂ̌o��͒��c�Ƃقړ����x�ł��邱�Ƃ��ψ���ł�������Ă��܂��B����S�ۂ���Έ��オ��ɂ͂Ȃ�Ȃ��̂ł��B����̂U����Ė��Ԉϑ��̃v���|�[�U���̎Q����Ƃ͓���22�ЁB���̒��ɂ́A�Ђ��炵�ۈ牀�ƎO�͓��ۈ牀�̋��H�𗎎D�������2�Ђ��Q�����Ă��܂��B�������A���̂Q�Ђ̂���1�Ђ͍ŏI�I�l��10�Ђɂ����ꂸ�A����1�Ђ��ŏI�I�l�Ɏc�������̂̌��Ǐ��6�Ђɗ��ЂƂ��c��܂���ł����B�����̈�ʋ������D�ɂ���āA���i�����ɂ��A�������Ǝ҂Ɉϑ��������Ƃ�����Ă��܂��B
�@���{�����ƐE���̑ސE�s��[�A���Ԉϑ����ȒʒB�Ŕ����Ă��Ă��܂����A����̍Ő�[�܂Ŏ��ׂ��������͂��ݎ����̂̎��含���F�߂��A�s�ꌴ���ŗD��������t���鐭�{�ɏ]���̂��Ƃ���A�斯�̍K�������V�X�e���ȂǂƂ͒������Ƃ���Ȃ���Ȃ�܂���B�����̂Ƃ��Ă̎��含�����A�����ɖ������d�˂閯�Ԉϑ��͒��~���ׂ��ł��B���������������B
�s���فt
�y�撷���فz
�@���I�T�[�r�X���ւ̎s�ꌴ���̓�����K���ɘa�ɂ��Ă̂�����ɂ������������܂��B
�@�ߔN�A�䂪���ł́A�o�ς̃O���[�o�����Ȃǂɔ����A�l�X�ȋK���ɘa�����i����Ă���A���I�T�[�r�X�̕���ł��s�ꉻ�e�X�g��w��Ǘ��Ґ��x���̓������i�߂��Ă���܂��B
�@��ʓI�ɁA�s���͑g�D�̔�剻�������Ȏ��Ǝ��s�Ɋׂ�₷���X��������A����Ɏ��~�߂�������ϓ_����A���Ԋ��͂̓�����i�߂邱�Ƃ́A�L���Ȏ�i�ł���ƌ����Ă���܂��B
�������A�����������ɂ����āA�ꕔ�̕s�S���Ȋ�Ƃ̎Q���ɂ��A��肪�����Ă��邱�Ƃ������ł���܂��B
�@���ɂ����������Ƃɂ��A�s�K�Ȏ������������ꍇ�A����ɑ������ɑΏ����A�������w�����Ă������Ƃ��A�斯�̐����ƍł����ڂȍs���@�ւł����b�����́A���Ȃ킿�A��̐Ӗ��ł���ƍl���܂��B
�@���̂悤�ȍl���̂��ƁA��Ƃ������܂��ẮA������A���I�T�[�r�X�ɖ��Ԋ��͂����p����ɂ������ẮA���Ɖ^�c��{�݊Ǘ����ɂ��āA������ɂ��߂���s�����N���邱�Ƃ̂Ȃ��悤�A����܂ňȏ�Ɍ��������O�R����A����̓K�ȃ`�F�b�N���s�����Ƃɂ��A�斯�̊F�l�̈��S�����A�s���T�[�r�X�̌����}���Ă܂��肽���ƍl���Ă���܂��B
�y�����������فz
�@�Ꮚ���҂ւ̉��ی����Ə��ɂ��āA�������������܂��B
��ł́A���݁A��z�̎l���̎O�S���Ă���������O�i�K�̒��ŁA�������S��\���~���������~���Z�\���~�����̕��ɂ��āA���ی�������z�̓̈�ɂ���A�Ƃ����y������u���Ă���܂��B
�@�܂��A�����\���N�x����A�W���I�ɂ͘Z�i�K�̕ی����敪�i�K�ɐݒ肵�A�斯�̊F�l�ɁA���\�͂ɉ������`�ł̕ی����̂����S�����肢���Ă���܂��B
���ی����x�́A���ׂĂ̍������݂��Ɏx���������Ƃ𗝔O�Ƃ��A���̔\�͂ɉ��������S�����Ă����������Ƃ���{�ƂȂ��Ă��鐧�x�ł������܂��B�܂��A��ʍ������J�����Ă̌��Ƃ͓K���łȂ��Ƃ���Ă��܂��B
�@�����̒Ⴂ���ł����Ă��A�y���������u������ŁA���̂����S�������������Ƃ��K�v�ł���ƔF�����Ă���܂��B
�y�q��Ďx���������فz
�@�q��Đ���ɑ���ƒ��������x�ɂ��Ă̂�����ɂ������������܂��B
�@�r���ɂ����܂��ẮA�q��Đ��オ�A���S���Ďq��Ă��ł��A�i���Z�ݑ��������Ǝ����ł���悤�A���܂��܂Ȋp�x����A�x������u���Ă���Ƃ���ł������܂��B���̂��߁A�q��Đ���ɏœ_�����Ă��Z��{��̂�������d�v�ȉۑ�ł���Ƒ����A���ݍ��蒆�́u�r���Z��}�X�^�[�v�����v�ɂ����܂��āA�q��Đ���ւ̑Ή��������ɓ���Ȃ���A�T�d�Ɍ������d�˂Ă���Ƃ���ł������܂��B
�@�������Ȃ���A�q��Đ����ΏۂƂ����ƒ��������x�ɂ��܂��ẮA���łɒ�ƒ��̌��c�Z���������Ă��邱�ƁA�P�Ȃ錻�����t�I�Ȏ{��͖]�܂����Ȃ����ƁA��Z��Ƃ��Ă̌��ʂ��K���������m�ł͂Ȃ����ƂȂǂ̗��R����A���x��n�݂��邱�Ƃ͍���ł���ƍl���Ă���܂��B
�y�����������فz
�@���ɁA��Q�Ҏ����x���@�Ɋւ��闘�p�ҕ��S���̂�����ɂ������������܂��B
�@��ł́A��Q�Ҏ����x���@�̎{�s�̍ۂɂ́A��Q�����T�[�r�X���p���̕��S�y�����тɒʏ��T�[�r�X���p�ɂ�����H����̕��S�y���ȂǁA�S���̎����̂ɐ�삯�čr���Ǝ��̌��ϊɘa������{���Ă܂���܂����B
�@����A���ɂ����܂��ẮA�Ⴊ���҂⎖�Ǝ҂̒u����Ă���܂��A��N�\�Ɂu��Q�Ҏ����x���@�̔��{�I�Ȍ������Ɍ������ً}�[�u�v�����肵�A���p�ҕ��S�̌������Ƃ��āA�����̒Ⴂ�Ⴊ���҂�Ⴊ���҂�����鐢�ѓ��ɂ��ẮA�{�N��������A����Ȃ镉�S�y����̎��{��\�肵�Ă���܂��B
�@��Ƃ������܂��ẮA���̓����𒍎����A����Ƃ��斯��l�ЂƂ�̏ɉ��������߂ׂ̍₩�ȑΉ���}���Ă܂��肽���ƍl���Ă������܂��B
�y�Ǘ��������فz
�@�p�����Čٗp���Ă�����ΐE���͐��K�ٗp�őΉ����邱�ƁA�Ƃ̎���ɂ������������܂��B
�@�搭���A�u�斯���K���ɂ���V�X�e���v�Ƃ��āA��{�\�z�Ɍf����u�K�������s�s�v�̎�����ڎw���Ă������߂ɂ́A�����w�傫���Ȃ��Ă����斯�̊��҂ɉ����āA�T�[�r�X�̌���Ƃ������I�Ȏ��s�̐��̊m���Ƃ��A�����Ď������Ă������Ƃ��K�v�ł���܂��B
�@�����āA���̒S����ł���E���W�c���A�ӗ~�Ɗ��͂ɖ����A���̂Ƃ��āA���̔\�͂����Ă������Ƃ��d�v���ƍl���Ă���܂��B
�@���̂��߂ɂ́A��ΐE���̈琬�ƂƂ��ɁA�_��ȋΖ��`�Ԃ̂��ƂɁA�l�X�ȕ���ŗD�ꂽ�\�͂����A���ΐE���̌��ʓI�Ȋ��p���A�傫�Ȍ���������̂ƍl���Ă���܂��B
�@��ł́A���������F���ɗ����āA���ΐE������ΐE���Ɠ��l�ɋ搭�̑�����S���҂Ƃ��ĉ��߂Ĉʒu�Â���ƂƂ��ɁA���̐E�ӂɌ����������x�Ƃ��Ă������߂ɁA�̗p�A�E���A��V�A���C�ȂǁA�����S�ʂɂ킽����ΐE�����x�̌��������s���Ă����Ƃ���ł������܂��B
�@����Ƃ��A��A���A���ꂼ��̓��F�������E���̐���z���A�搭��S���E���W�c�Ƃ��Ă̑����I�ȋ����ɓw�߂Ă܂���܂��B
�y������敔�����فz
�@�w��Ǘ��҂Ɋւ��邲����ɂ��Ă��������܂��B
�@��ł́A�����\�Z�N�x����A��̎{�݂ɂ��ď����w��Ǘ��Ґ��x�����A���݂ł́A�l�\�܂̎{�݂��w��Ǘ��҂ɂ��Ǘ��^�c���Ă���܂��B
�@�w��Ǘ��Ґ��x�́A���Ԏ��Ǝ҂̗L����m�E�n�E�����p���A�Z���T�[�r�X�̌����}�邱�Ƃ��傽��ړI�Ƃ��Ă���܂��B
�@���̂��߁A�w��Ǘ��҂ɂ́A���̍ٗʌ����ς˂��A�o�c�w�͂����Ă��炤���Ƃ����҂���Ă���ƂƂ��ɁA���킹�āA�����{�݂̊Ǘ���s�҂Ƃ��āA�����T�[�r�X�̈ꗃ��S������Ƃ��Ă̐Ӗ������߂��Ă���܂��B
�@����A�{�݂̊Ǘ��҂����́A�w��Ǘ��҂ɑ��Č��̎{�݂̓K���ȊǗ����m�ۂ��邽�߁A�@�ߏ���͂��Ƃ��A�Ǘ��^�c�̋Ɩ����m���ɗ��s����A���悢�T�[�r�X������Ă��邩�����`�F�b�N���邱�Ƃ����߂��Ă�����̂ł���܂��B
�@����܂ł��A��́A�I��̒i�K����A�w��Ǘ��҂ɑ��āA����������{�I�l�����𖾂炩�ɂ��A��{������тɔN�x������������ƂƂ��ɁA����I�ɕ����߁A���s���m�F���Ă܂���܂����B�܂��A���p�҃T�[�r�X�̌����}�邽�߁A�{�݂̗��p�҂ւ̃A���P�[�g�����{���A���Ԕc���ɓw�߂Ă���܂��B
�@����ɁA�w��Ǘ��҂Ƃ̘A�����݂��A�S�̉�c�ɂ́A�撷���炪�o�Ȃ��A�@�l���тɊe�{�݂̐ӔC�҂ɑ��A��̍l��������j�̎��m�O���}��ƂƂ��ɁA�S���҃��x���ɂ����Ă����X�̏��������ٖ��ɍs�����Ƃɂ��A��Ǝw��Ǘ��҂���̂ƂȂ��Ď{�݂̊Ǘ��^�c�ɂ������Ă���܂��B
�@������ɂ���܂������ɂ��܂��ẮA�ꕔ�̋Ɩ����w��Ǘ��҂����O�҂ֈϑ����邱�Ƃ�F�߂Ă���܂����A���̃P�[�X�ł́A��ւ̎��O�̏��F�葱�����Ȃ���Ă��Ȃ����Ƃ������������܂����B�܂��A��d�h���ɂ��܂��ẮA���̂悤�Ȏ����͂������܂���ł����B�����̌��ɂ��ẮA�w��Ǘ��҂Ɏw�����A���P���s�����Ƃ���ł������܂��B
�@���킹�āA��̑S�Ă̎w��Ǘ��{�݂�ΏۂɁA�葱���̘R���K�����������^�c���s���邱�Ƃ̂Ȃ��悤�A�����葱���̓O�����Ƃ̗͂��肽�`�F�b�N�@�\�̋�����}�邽�߁A��̎w��Ǘ��Ґ��x�^�p���j�̉�����Ƃ�i�߂Ă���Ƃ���ł������܂��B
�@��Ƃ������܂��ẮA������A�w��Ǘ��Ґ��x�������ʓI�Ɋ��p���A�斯�T�[�r�X�̈�w�̌���ɓw�߂Ă܂���܂��B
�y�q��Ďx���������فz
�@�����ۈ牀�̉^�c����������ɂ��܂��ẮA��c����͂��ߋ斯�̊F�l�ɑ�ς��S�z�����������Ă���܂����A��Ƃ��Ă��^�Ɉ⊶�ł���A�f�ł���p���������đΉ����čs�������ł������܂��B
�@�����̉^�c���������Ă̖��́A�@�����ق��ۈ�]���E���̔z�u���v�j�ɒ�߂������Ă��Ȃ����ƁA�A�N�Ԏw���v�悪�쐬����Ă��炸�A�ۈ�����̋L�^���e���s�\���ł��邱�ƁA�B�ۈ玺�ɂ���������Ɨc���Ƃ̃X�y�[�X�̋��̎d���A�X�ɁA�C�������̎�@�^�I����E�������p���Ă���Ȃljq���Ǘ����s�\���ł��邱�ƂȂǂł������܂��B
�@�����̖��ւ̑Ή��ɂ��āA���݁A�s�悪�A�g���ē������Ă���܂����A�F�ؕۈ珊�ɂ��ẮA�s�Ƌ�̖������S���������܂��B�����s�͕ۈ珊�J�݂ɂ������Ă̔F�̌�����L���A����Ɋ�Â��w���ē◧�����������s���܂��B�܂��A��ɂ��܂��ẮA�s�̍s�������A�w���ɗ�����ƂƂ��ɁA�ۈ珊�̉^�c��ɑ���⏕������t���A����ɁA�ۈ珊�Ɛg�߂ɂ��闧�ꂩ�����I�ۈ���e�ɂ��ď����A�w�����s�����ƂƂȂ��Ă���܂��B
�@����̎���ɂ��܂��Ă��A�������������s�y�ы�̂��ꂼ��̖������S�Ɋ�Â��A�ʂɂ��邢�͘A�g���āA������������P�w�������{���Ă����Ƃ���ł������܂��B
�@�����������ʁA�����_�܂łɁA��قnjf�������ɂ��܂��ẮA���̉��P������ꂽ�Ƃ���ł���܂����A�Ȃ������P�̓_������A�����������P�w���������߂Ă���Ƃ���ł������܂��B
�@�܂��A�⏕������t���Ă����Ƃ������܂��ẮA����̓s�Ƌ�ɂ�钲�����ʓ��ɂ��v�j�ɔ����鎖�������m�ɂȂ����ꍇ�ɂ͕⏕����Ԋ҂����邱�Ƃ��܂ߌ����ɑΉ����Ă܂��肽���Ƒ����܂��B
�@������ɂ������܂��Ă��A������Ƃ����ۈ珊�^�c���Ȃ���A�q�ǂ����������S�ʼn��K�ɕۈ炳���悤���������w���ēɑS�͂�s�����Ă܂���܂��B
�y�q��Ďx���������فz
�@�ۈ牀�Ɋւ���旧�E�Љ���@�l���̋��͑̐��ɂ��Ă̂�����ɂ��������܂��B
�@�������\�Z�̕ۈ牀�̒��ŁA�\�ꉀ�������ۈ牀���͌��ݖ��c���ł���A�o�c��̂́A������Ђł�����̂��ꉀ�A���͎Љ���@�l�ł���܂��B
�@��Ƃ��܂��ẮA�����\�ꉀ�ɑ��A�ǎ��ȕۈ�T�[�r�X���p���I�A����I�ɒ��邱�Ƃ���ɋ��߂Ă���Ƃ���ł���܂��B
�@���̂��߁A�\�ꉀ�̉����������o�[�ɘA�����݂��A��Ƃ̘A�g�̐����\�z���A���������^�c�̍l�����̎��m�O���}���Ă���܂��B�����ĉ������݊ԂŎ�̓I�ȋ��͑̐����~����Ă��܂��B
�@�܂��A���ݖ��c���̊e�w��Ǘ��҂ɑ��܂��ẮA�w��Ǘ��Ɩ��̊m���ȗ��s�ɑ���y�ъm�F�A���ѐR���Ȃǂ����{����ƂƂ��ɁA�ʂɏ���w���Ȃǂ��s���A���ߍׂ����^�c�̎w���ɓ������Ă���܂��B
�@������ɂ���܂����A�͂Ȃ݂����ۈ牀�ɂ��܂��ẮA�ۈ�m�̓���ւ�肪�������Ƃ�ٔN��ۈ�ɑ��܂��āA�ی�҂̊F�l���炲�S�z�̐�������܂������A�w��Ǘ��҂ɑ��Ďw�����A���P��}�����Ƃ���ł������܂��B�܂��A�����s�̎w�������ʼn��P��v���鎖���Ƃ���܂����������̔z�u�̖��ɂ��܂��Ă����łɉ��P����Ă���܂��B
�@������ɂ������܂��Ă��A��Ƃ������܂��ẮA�ݒu��̂ɌW��炸�A�r���̕ۈ牀�Ƃ��āA�q�ǂ����������S�ʼn��K�ɕۈ炳���悤�A���̉����E�w���̐��A���͑̐��̏[��������}���Ă܂���܂��B
�y�q��Ďx���������فz
�@�ۈ牀���̋��H�����Ɩ��̖��Ԉϑ��ɂ��Ă������������܂��B
�@�旧�ۈ牀�y�т��ǂ����ɂ����鋋�H�����Ɩ��̖��Ԉϑ��ɂ��܂��ẮA�h�{�m��z�u���邱�ƂƑ��܂��āA�H��̐��i�A�A�����M�[���Ή��̋����A���H���e�̏[���ȂǁA���H�T�[�r�X�̌����}��ƂƂ��Ɏ��{�̐��̌�������}�낤�Ƃ�����̂ł������܂��B���݁A�����Ɩ��̈ϑ������{���Ă�����̉��ɂ��܂��ẮA�����̖ړI�ǂ��苋�H�T�[�r�X�̌��オ�}���Ă���܂��B
�@���������ۈ牀���H�����Ɩ��̈ϑ��́A�����F�߂Ă���Ƃ���ł���A��Ƃ������܂��Ă��ӔC�������ċƖ���K�v�Ȓ��ӂ��ʂ�������̐���_����e�ɂ��A���H�̎��̊m�ۂɂ��Ė��S�������Ă���Ƃ���ł������܂��B�܂��A���N�l������̎�����҂̑I��ɂ�����܂��Ắu�v���|�[�U�������v��������A�����ɐR�����A�\���ȏ�����i�߂Ă���Ƃ���ł������܂��B
�@����ɂ��܂��Ă��A�ی�ҁA������ƎҁA�ۈ牀�E�ۈ�ۂ��A�g��}��A�q�ǂ������ɂƂ��Ĉ��S�ň��S�ȁA�����āA���������y�������H����邽�߁A���X�̉q���Ǘ��A�����w���͂��Ƃ�藚�s�̊m�F�A���؋y�ѕ]�������{���Ȃ���A�����A���H�����Ɩ��̈ϑ���i�߂ĎQ�肽���ƍl���Ă���܂��B
�s����t
�@��O�ɁA���闢�w�A�O�͓��w�̊X�Â���ɂ��Ă��f�����܂��B
�@�Ђ��炵�R�n��̍ĊJ���ł́A�����Ɣ�S�S�V���~�A�⏕���͂P�R�O���~�ɂȂ�܂����B
�������A�����̍��ی𗬓s�s�A���E�̌����A�R���V�F���W�F���闢�Ȃǂ̊|�����ɂӂ��킵���X�Â���ɂȂ����ł��傤���B�n�抈�����͂ǂ��������̂ł��傤���B���z�̐ŋ����������ꂽ���闢�w�O�ĊJ���ɂ��āA��Ƃ��ċ��P�Ƃ��ׂ����Ƃ͉����^���ɍl����ׂ��ł���܂��B�܂��A�O�͓��w�O��n��̂R�R�K���āA�P�Q�O���̍ĊJ���r�����A���H��P�R�W���~�A�⏕���R�Q���~���������v��ł����B���̍ĊJ���ɓ��闢�w�O�ł̐������ׂ����P�͂���̂ł��傤���B����͉����A����A��̌��������f�����܂��B
�@��ʃo���A�t���[�@��2000�N5���Ɍ��z����A�킪�}��c�c�́A���闢�w�̌�ʃo���A�t���[�@�w��Ɏ���グ��悤���߁A��������Ή����܂����B���̌��ʁA��{�v��̍���Ɠ��闢�w�\���̃o���A�t���[������|���ʂ�ȂǕ����̒i�������H���AJR���闢�w��������G�X�J���[�^�[�J�݂ɑ����A�G���x�[�^�[�J�݁A�܂��A�ɐl���C�i�[���闢�w���o���A�t���[������Ă��܂��B����ɁA��Q�҃g�C���̐ݒu�A�k�����D���R�[���R�[�X���L���A���邭�Ȃ������Ƃ͊��Ă��܂����A�K�v�ȉ��P�Ŏc���ꂽ�ۑ肪����܂��B
�@�ĊJ���r���͂R�K�����̃y�f�X�g���A���f�b�L�Ŏɐl���C�i�[�Ɛڑ����܂����A�������A���n��r���͂i�q���闢�w�̖ڂ̑O�Ȃ���Ԉ֎q�̕����s�����Ƃ���A����@�a�����������A3�K����1�K�ɍ~��āAJR���闢�w�����\���̃G���x�^�[���o�R���Ȃ�JR���闢�w�Ɍ���s�������Ȃ��\���ł��B
�@���n��̃e�i���g�́A�Q�K�́u���炪��v�A�����n����T�K�̃e�i���g�����܂��Ă��܂���B���ʓI�ɁA����₷���P�K�E�R�K�ȊO�̓e�i���g�U�v�����ł��B
�@�J�����ʂ���i�q�w�ɓ���ɂ́A�K�i�����ŃX���[�v���G�X�J���[�^�[���Ȃ��A����̊K�i�͐̂̂܂܂ŁA�����Ƃ̘A�����̐ݒu�͂ł���\���ɂȂ��Ă���ƌ������̂̂���͂��̂��Ƃ��c�A�Ђ��炵�R�n��Ƌ����R�w���H���⏕�����Őŋ����Q�Q�O���~�o����Ă��܂��B�ĊJ���A���闢�ɐl���C�i�[�H���A�����w�������P���Ƃ��I�����Ă���������̂́A����̂��Ƃł��傤�B���̂����A�o���A�t���[�̎��c���͐�ɋ�����܂���B
�@���Ẳ���B�a���̒����ɉ��f������ݒu��JR���闢�w�ɐڑ��ł���X���[�v�t�K�i�ݒu�����킹�čs�����ƁB����̋������闢�w�ڑ��Ɓu���݂����v�̃G�X�J���[�^�[�ݒu�ȂNJK�i�̕t���ւ��Ȃǂ��A�֘A���Ƃ̏I���܂łɁA�W���Ǝ҂ւ̍ő���̓��������������Ȃ��A��肫��Ƃ������f�����邱�Ƃ����߂܂��B��̌��������f�����܂��B
�@���킹�ċ��l���k���̉����^�]������̂Q�̉w��ʉ߂��Ă��܂��B���̎����ɁA���C�i�[���ƎҁE�����s��ڑ����鋞���ȂǂƂ����͂���JR�ɑ��ē��闢�w��Ԃ������\����邱�Ƃ����߂܂��B���������f�����܂��B
�@���ɁAJR�O�͓��w�̃o���A�t���[���ɂ��Ăł���܂��B�n��Z���̊F���A�G���x�[�^�[�Ɖ���G�X�J���[�^�[�ݒu�̑������������߁A��N�V�O�O�M������JR�ɒ�o���܂����B���̍ہA�G���x�[�^�[�ɂ��ẮA�r���Ƌ��c���Ȃ��瑁���ɐݒu�������ƉĂ��܂��B����̃G�X�J���[�^�[�ɂ��ẮAJR�͍���A�����Ă݂����Ƃ��Ă��܂��B���闢�w���ӍĊJ���̋��P�܂��A�ߗ��Ǝ҂�S�����p�҂ւ̍Œ���̗������P�ɁA�r���Ƃ��Ăi�q�O�͓��w�̃G���x�[�^�[�Ɖ���G�X�J���[�^�[���������̌��ӂ������Ă������������Ǝv���܂��B���������f�����܂��B
�@���ɁA���݂̍ĊJ���ւ̌������ƕ⏕�������ɂ��Ăł���܂��B���̍ĊJ���ɑ���⏕���x���������A�����Z��݂ɑ���⏕���x�ɐ�ւ���悤���߂�ׂ��Ǝv���܂��B���������f�����܂��B
�s���فt
�y�s�s�����������فz
�@�O�͓��w��k�̍ĊJ���v��Ɋւ��邲����ɂ��������܂��B
�@���闢�w���Ӓn��ł́A��́u���ƁE���j�v�Ƃ��āA���闢�E�ɐl���C�i�[�̓������_�@�ɎO�n��i�K�I���A���I�ȊX�Â����i�߂Ă܂���܂����B
�@������\�N�O���ɂ́A�V���̊J�Ƃɍ��킹�A���n��Ɉ������������n��̃r�����v�H���A�n��ɐl�X�����ӂ���킢���n�o����Ă܂���܂��B
�@�ĊJ���r���ɂ́A�������̍����{�݂Ƃ��āA���n��ɂ͏��q��哌��ÃZ���^�[�̓��闢�N���j�b�N�A�����n��ɂ͍r��s�Ŏ����������Ă܂���܂����B
�@�܂��A�����ĘA���f�b�L��������֏�Ȃǂ����A�n��ɍv������X�Â����i�߂Ă������̂ƔF�����Ă���܂��B
�@��ł͂��������F���̂��ƁA�O�͓��w�O�n��̍ĊJ���ɂ����܂��Ă��A��n��ł́A���͂���w�O�����`������~�n���̖S�u�̉w�O�L��A���|���ʂ�ɂ̓o�X�x�C�A�n��̕��u���]�ԑ�Ɋ�^����������֏�̐������s���\��ł������܂��B
�@�k�n��ɂ��܂��Ă��A�L��̐������n�ߒn��ɂӂ��킵�������{�݂̓�������������ȂǁA���闢�w�O�Ɉ��������n��Ɋ���ĊJ�����Ƃ����{���A�܂��̊������Ɍ��т��Ă��������ł������܂��B
�y�s�s�����������فz
�@���ɁA���闢�w���ӂ̃o���A�t���[���Ɋւ��邲����ɂ��Ă������������܂��B
�@����B�a���̂قڒ������ɉ��f������ݒu���邱�Ƃɂ��܂��ẮA��ʊǗ��҂Ƃ̋��c���I���A���݁A�N�x���̐ݒu��ڎw���Ď葱����i�߂Ă���܂��B
�@�o���A�t���[���̊ϓ_����́A���f�����̐ݒu�ɕ����āA�w�ɐڑ�����K�i�ƃX���[�v�����邱�Ƃ��K�v�s���ł��邱�Ƃ���A���ɂi�q�����{�Ƌ��c���n�߂Ă���Ƃ���ł������܂��B
�@�܂��A�����w�ɉ����ɍ��킹������ݒu�ɂ��܂��ẮA����܂ŋc���ĎO�v�����āA��Ƃ��Ă������d�S�ɑ��ėv�]���Ă���Ƃ���ł������܂��B
�@�����d�S����́A�n���v�]�ɂ������ݒu����ꍇ�́A�n�����S���K�v�Ƃ����Ă���A�����_�ł͓���ł������܂��B
�@���ɁA�u���݂����v�̃o���A�t���[���ɂ��܂��ẮA���̎��ӂɃG�X�J���[�^�[�E�G���x�[�^�[��ݒu����X�y�[�X���m�ۂł��Ȃ����߁A����ȏɂ������܂��B
�y�s�s�����������فz
�@���l���k�������d�Ԃ̓��闢�w��ԂɊւ��邲����ɂ������������܂��B
�@���闢�n��́A���闢�E�ɐl���C�i�[��c��`�ƎO�\����Œ������鐬�c�V�����S���̊J�ƁA����ɁA�Ђ��炵�̗��O�n��ł̎s�X�n�ĊJ�����ƂƂ����܂��āA�v�X���W�����҂���Ă���Ƃ���ł���܂��B
�@���̂悤�Ȓ��ŁA�����d�Ԃ̓��闢�w��Ԃ́A���闢�n�������ɁA�����̐l�X���W�����C�Ɩ��͂ɂ��ӂꂽ�X�Ƃ��Ă������߂ɂ��K�v�ƔF�����Ă���܂��̂ŁA���������i�q�����{�ɑ��܂��ėv�����Ă܂���܂��B
�y�s�s�����������فz
�@�i�q�O�͓��w�o���A�t���[���̂�����ɂ������������܂��B
�@���݁A�O�͓��w�ł͕����\�N�\�ɏ��̃G�X�J���[�^�[���ݒu���ꂽ�݂̂ŁA�ˑR�Ƃ��ăo���A�t���[�����i��ł��Ȃ��̂�����ł������܂��B
�@��ł́A�������������P���邽�߁A���˂Ă��i�q�ɑ��A�����ɃG���x�[�^�[�A����G�X�J���[�^�[�̐ݒu�������v�]�����Ă����Ƃ���ł������܂����A��N�\�ꌎ�ɂi�q�Ƌ�ŁA�G���x�[�^�[�A�G�X�J���[�^�[�̐ݒu�Ɍ�����̓I�ȋ��c���J�n�����Ƃ���ł������܂��B
�@���̌��ʁA�i�q����́A������\��N�܂łɁA�G���x�[�^�[�Ƒ��@�\�g�C���̐ݒu������������Ƃ̉Ă���Ƃ���ł������܂����A����G�X�J���[�^�[�̐ݒu�ɂ��܂��ẮA���݁A�Г��Ō������Ƃ̂��Ƃł������܂��B
�@��Ƃ������܂��ẮA����A���̋��c������ɐi�߁A�����Ƀo���A�t���[��������������悤�w�߂Ă܂���܂��B
�y�s�s�����������فz
�@���̌����Z��ݕ⏕���x�ɌW�邲����ɂ��������܂��B
�@�c��������̌����Z��݂Ȃǂɂ��Ă̕⏕���x�́A�n�������c�̂���̂ƂȂ�A�����Z��̌��ݓ����v��I�ɐ��i���邽�߂̎x�����x�Ƃ��āA�����\���N�x�ɒn��Z���t�����x���n�݂���Ă���܂��B
�@���̐��x�́A�n��ɂ�����Z�������含�Ƒn�ӍH�v���������Ȃ��瑍���I�ɐi�߂邽�߂̂��̂ł���A�⏕�����ׂ܂��Ă��A���闢�̍ĊJ�����ƂȂǂƓ����ȏ�ƂȂ��Ă���܂��̂ŁA�������̒��A��낵�����肢�������܂��B
�s����t
�@��l�ɁA����ɂ��Ăł���܂��B
�@�K�n�x�ʊw�K�ɂ��Ăł����A��b�w�͌���ɖ��ɂ������̂��������߂����Ǝv���܂��B����ψ���Ƃ��Ă��Z���́A���l�������V�N�x���{����Ƃ̂��Ƃł���܂����A�K�n�x�ʊw�K�ɌŎ�����̂łȂ��A���l��������͂��ߊw�Z����̔��f�ŁA���l�Ȋw�K���@�����{�ł���悤���P���ׂ��ł���܂��B�������������B
�@���ɁA���w�Z�̉p��Ȃ����{����ĂT�N�������܂��B���w�Z�P�N������̉p��Ȃ����������炵�����A�����ׂ����ł��B�����R�ł������w���̉p��Ȃ́A�u���w�Z5�N������v�Ƃ��āA�p��ɐe���ނ��Ƃ𒆐S�ɂ����Ă��܂��B�p��Ƌ����Ȃ����w�Z�̐搶�����ɐ����Ԃ̍u�K�Ŏ��Ƃ����{���Đ��K�ȖڂƂ��āA�]���܂ōs�����ɂ��܂������A���̕��Q��������Ă���Ǝv���܂��B�뜜����Ă����ʂ�A���w���̉p�ꌙ�������傳��Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�w�̓e�X�g�̌��ʂł��p��Ȃ̓��B�x�́A�T�O�����悤�ȏŁA�K�n�x���Ƃł���������Ԃ����Ƃ͂ł��Ă��܂���B
�@���Ȃ��Ƃ����w�Z��w�N�A���w�N�ɂ��ẮA�p��Ȃ��~�߂�ׂ��ł��B�������������B
�@�Ō�ɁA����ψ���́A�u�����w�Z�Z�ɐ����v��v�����肷�邽�߂ɁA�V�N�x�ɘV���������w�Z�̃R���N���[�g�������s�����Ƃɂ��Ă��܂����A����A���ւ��̑ΏۂɂȂ鏬���w�Z�́A�Q�T�Z�ɂȂ�悤�ł���܂��B�Z�ɐ����v�����ɍۂ��ẮA�w�Z�I�𐧂̌������Ə��l���̊w���Ґ�������ɓ��ꂽ�v��ɂ���悤���߂܂��B���������f�����܂��B
�@�ȏ�ŁA����ڂ̎�����I���܂��B
�s���فt
�y����ψ�����ǎ������فz
�@����{��Ɋւ��鎿��ɂ��������܂��B
�@�����\�l�N�x���A��l��l�̎q�ǂ��Ɋm���Ȋw�͂�g�ɂ������邱�Ƃ�ړI�Ƃ��A�{��ł͑S���ɐ�삯�ď��w�Z�O�N���ȏ�̎Z���E���w�Ɖp��ɂ��ďK�n�x�ʊw�K�����{���Ă��܂����B���̌��ʁA����܂ł́u�w�͌���̂��߂̒����v�ɂ����āA��b�w�͂̊m���Ȓ蒅�Ƃ������ʂ������Ă��܂��B
�@����ɁA���N�x�́u�Z���E���w��D�����i���Ɓv�𗧂��グ�A�w�K�i�x�̍���܂������ł��邾��������A�������т����������邽�߁A���w�Z�̈�A��N���̎Z���ɏ��l���w����e�B�[���e�B�[�`���O���������\��ł��B
�@����������Ă���V�����w�K�w���v�̂ł��A����܂ňȏ�ɂ��ߍׂ��Ȋw�K�w�������߂��Ă���܂��̂ŁA�w�Z����ƘA�g��[�߁A�����E���k�̔��B�i�K�ɓK�ɑΉ��������ʓI�Ȋw�K�w�����@�̂�������������ĎQ�肽���ƍl���Ă���܂��B
�y����ψ�����ǎ������فz
�@���w�Z�p�ꋳ��Ɋւ��邲����ɂ��������܂��B
�@�{��ł͍\�����v���ʋ��̔F����A�����\�Z�N�x������S���w�Z�A�S�w�N�ŏT���̉p��̎��Ƃ��s���Ă���A���N�x�Ŏl�N�ڂ��}���Ă���܂��B
�@���̊ԁA�{��Ǝ��́u�p��Ȏw���w�j�v�����肵�A�p����g���āA�R�~���j�P�[�V�������y���ނ��Ƃ��p�ꋳ��̖ڕW�Ƃ��āA�S�C���t���p�ꋳ��A�h�o�C�U�[��O���l�w�����ƂƂ��ɉp��Ɋ���e���ގ��Ƃ����グ�Ă܂���܂����B
�@���ɒ�E���w�N�ł́A�p����g���ĊO���l�Ɛg�̂܂��̂��Ƃɂ��ĉ�b��������A�����̋C������f���ɓ`���銈���Ȃǂɏd�_�������Ă���܂��B���̌��ʁA�O���l�u�t�ɐϋɓI�ɁA���R�Ȕ����������Řb��������q�ǂ����e�Z�Ō�����悤�ɂȂ��Ă��܂��B���w�Z��E���w�N�̎����̎q�ǂ��͉p��̉������������A�͕킷��\�͂������A�p����p��̂܂ܗ������邱�Ƃ��ł��A�{�悪�ڎw���u���H�I�R�~���j�P�[�V�����\�͂̈琬�v�ɂ����đ�ό��ʂ�������̂ƔF�����Ă���܂��B
�@�Ȃ��A�{��ł͂���܂ł̉p�ꋳ��̐��ʂƉۑ�������A������щp�ꋳ��̈�w�̏[����}�邽�߂̌����ψ��������ݒu����\��ł������܂��̂ŁA�������̒���낵�����肢�������܂��B
�y�����L���q��c�z
- �斯�̖��ƌ��N������Ð��x�ɂ���
- �V�T�ˈȏ�̌������҈�Ð��x�ŕی����ؔ[�҂ɂP�O�����S���Ȃ��鎑�i�ؖ����͔��s���Ȃ����ƁB
- �������Ґ��x�̕ی����̌��z�Ώۂ́A���ю����ł͂Ȃ���l��l��ΏۂɌ��z���s�Ȃ����ƁB
- �������҈�Ð��x�̕��Âɂ�鍷�ʈ�Â͌������K�v�Ȉ�Â�����悤�撷�Ƃ��Đ��{�ɗv�]���邱�ƁB
- �s����a�@�̉^�c��PF�h�����̖��ԉ^�c�ł͂Ȃ���ÂɊi�����Ȃ��n���ÂɕK�v�ȓs�����c�ʼn^�c���s�Ȃ��悤�����s�ɗv�����邱�ƁB
- ���ی����x�ɂƂ��Ȃ����P�ɂ���
- �����Ƌ�����҂ւ̉��T�[�r�X��̂Ă̐������A�����J���ȒʒB�Ɋ�Â��Ă��݂₩�Ɏ��{���邱�ƁB
- �u�Z���ŁE�����ł̍T���������Q�ҍT���F���\�����Ă��������v�̈ē������ׂẲ��ی����p�҂ɑ��t���邱�ƁB
- �w���N���u��w�[���̂��߂�
- ��K�͊w���N���u�͓K���K�͂̉��P�ɁA�ƂƂ��ɂR�����w�Z�E������w�Z�ȂNJw���N���u�̐ݒu�����邱�ƁB
- �w���N���u�ł̏�Q���Ή��͂U�N���܂Ŋg�[���邱�ƁB
- �n���ɂ₳�������̂��߂̒n������̂̎��g�݂ɂ���
- ����̂b�O2�팸�ڕW�ƌv��𖾂炩�ɂ��邱�ƁB�܂��A�����{�݂̂b�O2�팸�����߂����ƁB
- ����̑�C���������Ɖ��P�v������Ă邱�ƁB
- �����������~�߂悤�L�����y�[�����{���邱�ƁB
- �H�Ɨp���̗��p�p���ƕK�v�ȑ�ɂ��ē����s�ɓ��������邱��
�s����t
�@���͓��{���Y�}��c�c�Ƃ��Ĉ�ʎ�����s�Ȃ��܂��B
�@���ɋ斯�̖��ƌ��N������Ð��x�ɂ��Ăł��B
�@�������҈�Ð��x�����悢��S�����{���}���悤�Ƃ��Ă��܂��B�����J���Ȃ́A���S�̌������E��������}�邱�ƁA����Ô�̗}����}�邱�Ƃ�ړI�Ƃ��āA�Ŏ���Ō�̏u�Ԃ܂ł̏d�v�Ȉ�Ís�ׂ��K�v�ȁA�V�T�ˈȏ�̍���҂��A�������҂ƃl�[�~���O���đS�Ă̍���҂������I�����������܂��B�܂��A�ی����͐��тł͂Ȃ��A�ЂƂ�ЂƂ�ɂ�����A�N������V��������܂��B����ɕی����������Q�N���Ƃɍs���A�m���ɒl�グ�����������ł��B
�@�V�l�ی��@�ł́A����҂̈�Â̕K�v���E�d�v������ی����ؔ[�����ی��̕Ԋ҂Ǝ��i�ؖ����̔��s�͍s��Ȃ����ƂɂȂ��Ă��܂������A�V���x�ł́A�����Ԃ̕ی����ؔ[�𗝗R�ɂV�T�ˈȏ�̕��̕ی��ؕԊ҂Ǝ��i�ؖ����̔��s���s���邱�ƂɂȂ�܂��B�@�ی����t�͈̔͂����x�z�����߂���z���ň�Â̐����ɂȂ�Ɗ뜜����Ă��܂��B
�@���̓��e���`���قǂɁu�N���͑������˂ƌ������Ƃ��v�ƕs���̐����L�����Ă��܂��B���{���Y�}�͍��Ɍ����Đ��x�̒��~�P������߂�ƂƂ��ɁA��������ی������͂��ߐ��x�̌����������߂Ă��܂����B�撷�͂��߁A�����́E�c��̓w�͂������Ĉ��̌��������o�������Ƃ͊�т����Ǝv���܂����A���{�I�Ȗ�������A���_�����₵�܂��B
�@���͕ی��̕Ԋ҂Ǝ��i�ؖ����̔��s�ł��B�ؔ[����������̂́A���P���T��~�ȉ��̔N���̕��△�N���̒Ꮚ���̕��ł��B�����̕��X�̑ؔ[�́A�������Z����܂Ő�߂Ă������Ȃ��悤�Ȏ��Ԃ������̂ł͂Ȃ��ł��傤���A���ϗ]���܂ŐՐ��N�̑��y�����ɁA�s����^���A��҂ɂ��s���Ȃ��悤�ȏ����͂����čs���Ȃ���Ȃ�܂���B���i�ؖ����̔��s�͍s��Ȃ���̌��f�����߂܂��B�������f���܂��B�@
�@���͌y���[�u�ɂ��Ăł��B�L��A���ł̋c�_�̐��ʂƂ��āA�ϓ����R�V�W�O�O�~�̂V���E�T���E�Q�����z�ƈ�ʐŌ����������āA�������ɂ��Ă���N�ԂɌ���S�i�K�Ō��z���邱�ƂɂȂ�܂����B
�@�������A�ی����͈�l�ЂƂ�Ȃ̂ɋϓ�����̌��z�́A���т̏����Ō��邱�Ƃɂ���A�����N���z�Ȃ̂ɋϓ������z������l�Ǝ��Ȃ������ł܂��B���̔N�������̂��邲��l�Ƃ̕v�w���сA���q�E���̕}�{�ɂȂ��Ă��铯�����тł����A�Ƒ��ƈꏏ�ɂ��邱�Ƃ���ׂȂ��悤�Ȏd�g�݂͗ǂ�����܂���B�ϓ����茸�z����l�ЂƂ�̏����Ō��߂�悤�ɂ��ׂ��Ǝv���܂��B���ق����߂܂��B
�@��O�͎��Â̓��e�ɂ��Ăł��B�S������̐f�Õ�V�̉���ɂ��Ē����Љ�ی���Ë��c����\���o���܂����B
�@�������҂̕��̈�Ó��e�́A���A�a�⍂�����A�ߏ�Q���A���������̐f�@�͈�̈�Ë@�ւ����߁A�f�@�A�����͌��x�z�����߂���z���ɂȂ�܂��B����҂������������Œ����Ԓʉ@����P�[�X�������A�����̕a�@�œ��������Ⓤ�s���邱�Ƃ́A���P���ׂ��ł����A��������z��Âʼnʂ����āA�K�v�Ȉ�Â�����̂��A��Ë@�ւ́A�V�T�Έȏ�̍���҂ɂ͌����Ȃǂ��Ȃ��ōς܂��悤�Ȃ��ƂɂȂ�Ȃ����뜜����܂��B
�@�����������×{�a�����Q�O�P�Q�N�܂łɂR�W��������P�T�����ɍ팸����v�悪�i��ł��āA���@�����Â炢�Ƃ������A�]�@�𔗂��Ă�����������̂ł��B���킹�ĉ̂ނ����������҂̏I������Âɂ��āA�ߏ��Â��s��Ȃ��悤�Ȑf�Õ�V�ɂ���Ƃ������x����������܂��B����������Â�]�܂Ȃ���������ł��傤�B
�@�������A�ߏ�Ȉ�ÂȂǂ���̂ł��傤���H�Ō�܂Ől�Ԃ炵����Ís�ׂ��a�@�ł��ݑ�K�v���Ǝv���܂��B�������҈�Â̕��ÂȂǂ��������V�T�Έȏ�̕����K�v�Ȉ�Â�����悤�W�@�ւɗv�]���邱�Ƃ����߂܂��B���������������B
�@���ɍr��斯�ɂƂ��Ă��M�d�ȕa�@�ł���s����a�@�ɂ��Ďf���܂��B
�@�����s�͉c����Ǝ哱�̂o�e�h���������A�O�H�����ɋ�a�@�̉��z�Ƃ��̌�̉^�c���Q�O�N�Ԃɂ킽���Ă܂�����_������т܂����B���A���{�̎哱�������Ēn��̌��c��Ë@�ւ̍ĕҁE�l�b�g���[�N���ƌo�c�������𗝗R�ɉc����Ƃ̎Q�����S���Ői��ł��܂��B�������A���m�����͂��ߌo�c�̈������Ís�ׂ̒��f�Ȃǂ̎��Ԃ������N�����Ă��܂��B
�@�o�e�h�����ł́A�����s�͌������̕ԍςƕa�@�^�c�_������ɓn���Ďx�������̂ł����A��Ƃ́A��Ís�ׂɊ֘A�����A���҂̋��H�A���|�A��Î����Ȃǂ����Ɉ������v�������邱�ƂɂȂ�܂��B�s���̖�������a�@�̖������ʂ����邩�S�z�ł��B
�@�S�����̖{�i�I�o�e�h�����Ƃ��Ē��ڂ��W�߂��u�ߍ]�����s��������ÃZ���^�[�v�́A���{��킸����N���ŐԎ������A�V���ȍČ��v�悪�K�v�ɂȂ�܂����B�܂����m��ÃZ���^�[�ł͑����d�������N����A�u�a�@���Ԏ��ł��^�c��Ƃ͍����E�o�c���e���ł̒��ցv�ƕ���܂����B
�@���E�́A�u���{�Y�ƃv���W�F�N�g���c��v�������グ�A�����̕a�@�̂o�e�h����Ɨ��s���@�l���ɂ��đ傫�ȃr�W�l�X�`�����X���Ƃ��Ă��܂��B����A����Ȃ�K���ɘa�����߁A�a�@�o�c�S�̂̊�����ЎQ�����i�ނƂ�����斯�E�s���̈�Â͂ǂ��Ȃ�̂ł��傤���B
�S���̐�s��ł����_���I�悵�Ă���A���̂܂܋�a�@�̂o�e�h�����������߂Ă͂Ȃ�Ȃ��Ǝv���܂��B
�@�s����a�@�́A�P�Q�O�N�̗��j������A����E�������Â����ł͂Ȃ������a�@�Ƃ��ċߗגn��̒��j�a�@�ł��B�r�����̕a�@��f�Ï��Ȃǂ���Љ��ŋ�a�@����f����Ă�����������̂ł��B���̌v��������Ă���s���͏��Ȃ��Ǝv���܂����A���|�I�ɂ͍��̉^�c���[�����邱�Ƃ���]���Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�s����a�@�̉^�c��PFI�����̖��ԉ^�c�ł͂Ȃ��s�����c�ʼn^�c���s�Ȃ��悤�����s�ɗv�����邱�Ƌ��߂܂��B���������������B
�s���فt
�y�撷���فz
�@��Ð��x�ɂ��Ă̂�����ɂ������������܂��B
�@�}���ɏ��q������i�W���钆�ŁA�䂪���̈�Ð��x�������ɂ킽�莝���\�Ȃ��̂ɕϊv���Ă������Ƃ����ړI�ŁA�{�N�l������A�V���Ȍ������҈�Ð��x���X�^�[�g�������܂��B
�@�{���x�ɂ��܂��ẮA��N����A��ی��҂����S����ی�������Ș_�_�Ƃ��āA�c��̊F�l�Ɨl�X�ȋc�_���s���Ă܂���܂����B���̊ԁA���́A���ʋ撷���L��A�����c��̏�Ȃǂɂ����āA��������ی����̈�����������т��Ď咣���Ă܂���܂����B
�@�c��̊F�l����A���x�����̈ӌ�������o���ꂽ���Ƃ�����A�{�N�ꌎ��\�l���ɊJ�Â��ꂽ�L��A�����c��ɂ����āA�@��̕ی����y���[�u�ƍL��A���Ǝ��̓��ʑ�ɉ����A�u����Ȃ�Ꮚ���ґ�v�����{���邱�Ƃ����肳��܂����B
�@���̌��ʁA�������҈�Ð��x�̈�l������̎������ϕی����́A�N�z�������O�S�~�ƂȂ�A�����̎��Z�Ɣ�r���āA�啝�Ɉ����������܂����B
�@���݁A�l���̃X�^�[�g�Ɍ����A������Ƃ��}�s�b�`�Ői�߂�ƂƂ��ɁA�斯�̊F�l�ɑ��鐧�x�̎��m�ɓw�߂Ă���Ƃ���ł������܂��B
�@�����̗v�ȓ_�́A�V���Ȑ��x���Ȃ��^�p���A�斯�̊F�l�ɖ��p�Ȃ��s���₲�S�z�������Ȃ����Ƃł���ƔF�����Ă���܂��B�S����ۂƂȂ��āA���x�̉~���ȉ^�p�ɓw�߂Ă܂���܂��B
�y�����������فz
�@�������҈�Ð��x�ɂ����鎑�i�ؖ����̔��s�ɂ��Ă̂�����ɂ������������܂��B
�@�������҈�Ð��x�ɂ����ẮA��ی��ҊԂ̌������Ɛ��x�̈��萫���m�ۂ��邽�߁A�ی������x�������Ƃ��ł��Ȃ����ʂȎ���Ȃ��ɂ�������炸�A�ی�����ؔ[���Ă����ی��҂ɂ͎��i�ؖ����s���A���ҕ����ɂ�苋�t���s���܂��B
�@�ЊQ�ⓐ��A��ی��҂܂��͐��v����ɂ���e���̕a�C�E�����A���ю傪���Ƃ�p�~�܂��͋x�~�����ꍇ�ȂǓ��ʂȎ������ꍇ�́A���i�ؖ����͔��s�������܂���B
�@���̎��i�ؖ����ɂ��āA�ی��҂ł���L��A���́A��t�R���ψ����݂��A��t��̌��i���T�d�ȉ^�p���s���A�@�B�I�ɔ��s���邱�Ƃ̂Ȃ��悤�T�d�ɑΉ�����Ƃ��Ă���܂��B
�y�����������فz
�@���ɁA�������҈�Ð��x�ɂ�����ی����̌��z��ɂ��Ă̂�����ɂ������������܂��B
�@�������҈�Ð��x�ɂ����܂��ẮA���������ȉ��̔�ی��҂ɂ��āA�ϓ����ی������y�����邱�ƂƂȂ��Ă���܂��B
�@�y�������́A�����A�܊��A�Ƃ���Ă���A���ꐢ�ѓ��̔�ی��ҋy�ѐ��ю�̑��������z���Ɋ�Â��Ĕ��肪�s���܂��B
�@���������ی����̌y�����x�ɂ��܂��ẮA�@�߂̋K��Ɋ�Â����{������̂ł��邽�߁A�l�P�ʂ̏����Ō��z���肷�邱�Ƃ͍���ł���܂��B
�y�����������فz
�@ �������҈�Ð��x�ɂ������Â̒ɂ��Ă̂�����ɂ������������܂��B
�������҈�Ð��x�ɂ������Â̒ɂ��ẮA��N�\���ɎЉ�ۏ�R�c��̓��ʕ���ɂ��f�Õ�V�̌n�̍��q�����܂Ƃ߂��Ă���܂��B
�@�O����Âɂ��ẮA�厡�オ�A���҂̕a���⑼�̈�Ë@�ւł̎�f�̔c���y�ъ�{�I�ȓ��퐶���̔\�͓��ɂ��đ����I�ȕ]�����s���A�×{����w���Ŋ��p���邱�ƁA�܂��A���I�Ȏ��Â��K�v�ȏꍇ�ɂ́A�K�Ȉ�Ë@�ւɏЉ��Ȃǂ̖������ʂ������Ƃ����߂��Ă��܂��B
�@����A�����Љ�ی���Ë��c��炻�̍��q�ɉ������f�Õ�V����̓��\���o����܂����B���̓��\�ɂ́A�������҈�Â̐f�Õ�V������҂̐S�g�̓����ɉ�������ÒɎ�������̂ƂȂ��Ă��邩�Ƃ����ϓ_����A���{��̏ɂ��Č����s���ׂ��Ƃ̈ӌ����t����Ă��܂��B
�@��Ƃ������܂��ẮA���������A���̓����𒍈Ӑ[��������Ă܂��鏊���ł���܂��B
�y���N�S���������فz
�@�斯�̖��ƌ��N������Ð��x�̂�����̂����A�s����a�@�̉^�c�Ɋւ��邨�q�˂ɂ������������܂��B
�@�����s�ł́A�z�O�\�N���o�߂��ĘV�����̐i��ł����a�@�ɂ��܂��āA��Ê��̏[����}�邽�߁A�S�ʓI�Ȍ������C�����{����\��ł������܂��B
�����āA���݂̊�Ջ@�\�����p�������܂��āA����含�����߂āA����Ɗ����Lj�ẪZ���^�[�@�\��L����a�@�Ƃ��Đ�����}��ƂƂ��ɁA���������n���ÂƂ̘A�g�ɂ��w�߂Ă������ƂƂ��Ă���܂��B
�@���̂��т̐�����@�Ƃ��ē��������a�@�̂o�e�h���Ƃ́A�f�ËƖ��ɂ��Ă͓s�ɂ�钼�c���ێ����A������̋ߍ]�����s��������ÃZ���^�[�⍂�m��ÃZ���^�[�̗�Ƃ͈قȂ�A�s���a�@�{�݂����L�����܂܁A���Ԏ��Ǝ҂��V�������������{�݂̉��C�ƁA�ێ��Ǘ���^�c���s���q�n�����ɂ����̂ł������܂��B
�@�܂��A�c�������O����Ă���悤�ȁA���Ԏ��Ǝ҂��a�@�o�c�ɎQ�悷��悤�Ȃ��Ƃ͓s�Ƃ��Ă��z�肵�Ă��Ȃ��ƕ����Ă���Ƃ���ł��B
��N�\�ɂ́A�s�Ɩ��Ԏ��Ǝ҂Ƃ̊ԂŌ_��������Ă���܂����A��Ƃ������܂��ẮA���p�҂��s���������邱�Ƃ��Ȃ��悤�A�s�ɂ͓K�ȏ��������Ă܂��肽���ƍl���Ă���܂��B
�s����t
�@���ɉ��ی����x�̉��P��ɂ��Ăł��B
�@���ɁA�����Ƌ�����҂ւ̉��T�[�r�X�ɂ��Ăł��B
�����J���Ȃ���N�P�Q���Ɂu�ʋ�̓I�ȏ܂��Ȃ��œ����Ƒ������邱�Ƃ݂̂f��Ƃ��Ĉꗥ�@�B�I�ɃT�[�r�X���t�̉ۂ����肵�Ă������Ă���v�Ƃ��āA�u�X�̗��p�҂̏ɉ����ēK�ɔ��f���邱�Ɓv�Ƃ����ʒB���o����܂����B�r�������̒ʒB�Ɋ�Â��Ď��{����悤���߂܂��B���������������B
�@���ɉ��ی��v���҂�����̂̔F�����Ώ�Q�Ҏ蒠���Ȃ��Ă���Q�҂ɏ����ď����ŁE�Z���ł̍T��������u��Q�ҍT���Ώ۔F��v�ɂ��Ăł��B
�@��Ƃ��Ă��̏�Q�ҍT���Ώ۔F��ɂ��Ă͎��ǂ��̗v�]�ɓ����Ă���������������Ɍf�ڂ��ꂽ���ł��B�F�茏���͈ꌅ�̐\������f�ڂƂƂ��ɂO�T�N�U�Q���E�O�U�N�X�V���ƍT����������������Ă��܂��B���̂��A�V��ҍT���̂T�O���~�������Ȃ��đ��łŕی����ɂ܂ŘA�����ĊF�����ς�����ł��B���߂āA�g����T���̕��@���炢�͋�Ƃ��ē��������m�点���ĉ������B
�@���c�J��ł͑S�Ώۂ̕��ɂ��̂��m�点���o�������Ƃňꌅ����R���̐\���ɂȂ��������ł��B������ł����l�̒ʒm�����S�Ώێ҂ɗX�����Ă��܂��B
�@�r���ł������҂��m��Ȃ������Ƃ������ɂȂ�Ȃ��悤�ΏێґS���ɂ��m�点�𑗕t���邱�Ƃɂ��Ă��������������B
�s���فt
�y�����������فz
�@���ɁA�����Ƌ�����҂ւ̉��T�[�r�X�ɂ��āA�������������܂��B
�@�����\��N�\��\���ɁA�����J���Ȃ���A�u�����Ƒ���������ꍇ�ɂ�����K����T�[�r�X����щ��\�h�K����T�[�r�X�̐����������̎戵�ɂ��āv�̎����A��������܂����B
�@���ی����x�̐����������́A�P�g���͉Ƒ�������Q�A���a�A���̑����l�̂�ނȂ�����ɂ��A���Y���p�Җ��͉Ƒ������Ǝ����s�����Ƃ�����ł���ꍇ�ɍs���邱�ƂƂȂ��Ă���A�ʋ�̓I�ȏ܂��Ȃ��ŁA�����Ƒ����̗L���݂̂f��Ƃ��āA�ꗥ�@�B�I�ɉ�싋�t�̎x���̉ۂ����߂邱�Ƃ̂Ȃ��悤�ɂƂ������Ƃ��A���炽�߂ēO�ꂵ�����̂ł������܂��B
�@��ɂ����܂��ẮA����܂ł��A���ی����x�̎�|�܂��A���������ɂ��āA�ʋ�̓I���m�F���Ȃ���A���ی���̕K�v���m�ɂ��čs���悤�w�����Ă����Ƃ���ł������܂��B
�@����Ƃ��A�X�̏ɉ����A�K�v�ȕ��ɕK�v�ȉ��T�[�r�X���K�ɒ����悤�w�߂Ă܂���܂��B
�y�����������فz
�@���ɁA��Q�ҍT���F��ɂ��Ă̂�����ɂ������������܂��B
�@�����Ŗ@�{�s�ߓ��̋K��ɂ��A����҂ɂ��ẮA��s���������m�I��Q�҂܂��͐g�̏�Q�҂ɏ�����҂Ƃ��ĔF�肵���ꍇ�ɂ́A���ʏ�Q�҂��Q�҂̍T�����邱�Ƃ��ł��܂��B
�@���̂��߁A��ł́A���ی��̗v���F����Ă��鍂��҂�ΏۂƂ��āA���ʏ�Q�҂܂��͏�Q�҂̔F��\���̎�t���s���Ă���܂��B
�@���̏�Q�ҍT���̔F��ɓ�����A�u�v���F��v�Ɓu��Q�F��v�ɂ��ẮA���̔��f����قȂ���̂ł���A�v���F��̌��ʂ݂̂������āA�ꗥ�ɒm�I��Q�҂܂��͐g�̏�Q�҂ɑ�������̂��ǂ����f���邱�Ƃ�����ł��邽�߁A���ی��̗��p�ґS���ɁA���x�̈ē��𑗂邱�Ƃ͓K���ł͂Ȃ��ƍl���Ă���܂��B�@
�@���������܂��āA��Q�ҍT�����x�̎��m�ɂ��܂��ẮA����܂łƓ��l�ɁA����z�[���y�[�W���ɂ��s���Ă܂��鏊���ł������܂��B
�s����t
�@��O�͊w���N���u�̈�w�̏[���ɂ��Ăł��B
�@�����Ȃ���q��Ă�����ƒ�ɂƂ��Ċw���ۈ�N���u�͕ۈ珊�Ɠ����悤�ɂ͂Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����Ƃł��B
�@ �w���ۈ�N���u�݂��Ă��܂������A���̎��v�͍��܂�����2001�N�V�O�O���]�����݂͂P�Q�T�O�����Ă��܂��B�ۗ������o���Ȃ��ς��ɃN���u�̑�͉����i����ł��܂��B
�@�q�ǂ�����������Ă��×{����ꏊ���Ȃ��A�w�����̊�����Ȃ��ȂNj�̓I�����w�E����Ă��܂��B�����J���Ȃ͂Q�O�O�V�N�Ɂu��K�͊w���N���u�͎q�ǂ��̏�������S�m�ۂ̊ϓ_����v�������邱�Ƃ��K�v�Ƃ̕��j��ł��o���A�R�N�Ԃ̌o�ߑ[�u�������ĂV�P�l�ȏ�ւ̕⏕���ł���[�u�����߂Ă��܂��B�w���ۈ玖�Ƃ̓K���K�͂͋��ʔF���ɂȂ��Ă��Ă���A�Q�O�P�O�N���}����O�ɕ������ĂV�O�l�ȉ��ɂ��邱�Ƃ��҂����Ȃ��̉ۑ�ł��B
�@�S���w���ۈ�A����c��̒����ɂ��܂��ƂP�N������R�N���A��w�N�̎q���w���N���u�ʼn߂������Ԃ͉ċx�݂͒�����s���܂�����N�ԂP�U�O�O���ԂƊw�Z�ɂ��鎞��蒷���̂ł��B�����̏�Ƃ��Ă̎��I����ƈ��S�m�ۂ̖ʂ����K�̓N���u�̉��P�Ɏ��g�ނ��Ƃ����߂܂��B
�@���킹�ď��w�Z��ɑΉ�����w���N���u���Ȃ���O�������w�Z�A�P�����w�Z�̊w���N���u�ݒu���������Ă��������B��O�������w�Z�̎q�ǂ������͓��Z�E���Z�S���ځE�����E���E�������e�N���u�R�R���̎q�ǂ��������A���Z�n��̂��������ɕ��U���Ă��܂��B
�@�P�����w�Z�ł͐V�N�x������ی�S��������n�߂܂����A�S������ƕۈ�Ɍ�����N���u�̎��Ƃ͐������Ⴂ�܂��B�����ݒu�v������������������B
�@���ɏ�Q���̎���ɂ��Ăł��B�r���͌��݂S�N���܂łƂȂ��Ă��܂��B��N�̂T���P�����݂ł͂P�U�J���Q�X���̎���������Ă��܂��B�e�䂳��T�N�U�N�ɂȂ�����ǂ������炢���̂��B�S�z�łȂ�Ȃ��Ƃ��Č��ݒʏ����Ă���S�N���̕ی�҂���v�]���o����Ă���ƕ����Ă��܂��B�Q�R��ł��P�S��͂��łɏ��w�Z���Ƃ܂Ŏ��{���Ă��܂��B���̎��X�̑Ή��ł͂Ȃ��U�N�܂Ő��x�Ƃ��đΏۂ��g�債�Ē��������Ǝv���܂��B�������������B
�s���فt
�y�����������فz
�@�w���N���u�ɂ��Ă̂�����ɂ������������܂��B
�@�w���N���u�ւ̃j�[�Y�͔N�X�����Ă���A��Ƃ������܂��ẮA����܂ŋ���ψ����w�Z�ƘA�g��}��Ȃ���w���N���u�̑��݂ɓw�߂Ă����Ƃ���ł������܂��B�����Z�N�x�ɂ͏\�O�N���u�A����l�l�Z�l�ł������Ƃ���A���݂͓�\�l�N���u�A������Z�ܐl�ɂ܂Ŋg�債�Ă܂���܂����B
�@���������̒��A����ɒ������w���N���u������A��Ƃ������܂��ẮA�ҋ@�������o���Ȃ����Ƃ���j�Ƃ��Ă��邽�߁A����ȏ�̎�����s���ꍇ�ɂ́A����E���z�u�ɗ��ӂ��A�H�v�������Ȃ��������s���Ă܂��肽���Ƒ����܂��B
�@�܂��A����Ƃ��A�q�ǂ����������S���Ă����₩�ɕ��ی���߂�����悤�A���̕��ی㎙���N���u�K�C�h���C���̎�|�����܂��A����ψ����w�Z�ƘA�g���Ƃ�Ȃ���w���N���u�̊������ȂǁA���̏[���ɓw�߂Ă܂���܂��B
�@�Ȃ��A��O�������w�Z�E�����闢���w�Z���ɂ��Ăł������܂����A�����闢���w�Z�ɂ��܂��ẮA������\�N�x������ی�q�ǂ��v���������{���Ă܂���܂��B�܂��A��O�������w�Z�ɂ��܂��ẮA�w�Z���̂̎������̐L�т�{�݂̏���A�w���N���u�̐ݒu�͓�����������܂��B����Ƃ��l�X�Ȏ��_����Ή����������Ă܂��肽���ƍl���Ă���܂��̂ł����������肢�������܂��B
�y�q��Ďx���������فz
�@�w���N���u�̏Ⴊ�����̑Ή��ɂ��Ă̂�����ɂ������������܂��B
�@���݁A�w���N���u�ł͏Ⴊ���̂��鎙���ɂ��܂��Ă͏��w�Z�l�N���܂Ŏ���Ă���܂��B�������A�ی�҂̏A�J�̕ω��ɂ��A�Ⴊ���������ی�҂��A�J����Ⴊ�����Ȃ�A�ܔN���ȏ�ɂȂ鎙���̕��ی�̉߂��������l����K�v�������Ă܂���܂����B
�@�ܔN���ȏ�̏Ⴊ�����������ꍇ�A�����̐g�̓I�E���_�I�����ɍ��킹���w���v���O�����̍���A�E���z�u�Ǝw���̐��A��p�X�y�[�X���̎{�ݐ����ȂǁA�������̉ۑ肪�l�����܂��B��Ƃ������܂��ẮA���������ۑ�̌������s���Ď��{���Ă��鑼��̏����Ȃǂ�i�߂Ă܂��肽���ƍl���Ă���܂��B
�@������ɂ������܂��Ă��A�Ⴊ���̂��鎙���̎���ɂ��܂��ẮA�������E����ψ���ƘA�g���A�Z�N���܂ł̎���Ԑ��̐�����A�^�C���P�A���ƂȂǂ̑��̐��x������ɓ��ꂽ���ی�����S�̂Ō������Ă܂��肽���Ƒ����܂��̂ŁA�������̂قǂ��肢�������܂��B
�s����t
�@���ɒn���ɂ₳�������̂��߂̒n�������̂̎��g�݂ɂ��Ă��������܂��B
�@�r���͊���i�s�s�Ƃ��ċ撷�̏��M�\���ł��u���������[�h������{��̔��M���s���A���ƗɌb�܂ꂽ�������̐������߂����v�Ƃ��Ċ���{����݂ǂ�̊�{�v��̍����V�N�x���j�ɐ��荞�݂܂����B
�@�����̂ɂ��Ă͒n�����g�������i�@�Ŏ���̎����E���ƂɊւ��鉷�����ʃK�X�̔r�o�}���̎��s�v������肷��Ƌ��ɂ��̎��{�����\���邱�Ƃ��`���Â����Ă��܂��B
�@�܂��n��S�̂̑����I�v������肵���{�ɓw�߂邱�Ƃ����߂��A��N�R���ɂ͊��Ȃ������̂ɂ����鉷�����ʃK�X�r�o�ʎZ���@���̂������������Ă��܂��B
�@�匳����}�����邱�Ƃ���Ԃł����A�����̂Ƃ��čs������A�ƒ납��̔r�o�}���A���ƎҁA�^�A���傻�ꂼ��̐��l�ڕW����������̓I�Ɏ��g�ނ��Ƃ����߂���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B����̂b�n�Q�̍팸���l�ڕW�ƌv��𖾂炩�ɂ��邱�ƁB�܂��A��{�ƂȂ�ׂ������{�݂̂b�O2�팸����̉����邱�ƁB���������������B
�@���ɑ�C�������ł��B����̏����w���̂��늳���̍������ȑO�w�E�v���܂����B�S���ł��V�N�A���ő������Ă��܂��B��C�����͎������̌��N�Ȃ������łȂ��n�����g���ɂ��Ȃ���ȂǁA�l�X�Ȗ��_���܂�ł��܂��B��C������̎��{�v��ƂƂ��Ɍ����𖾂炩�ɂ��钲���Ɖ��P�v������߂���̂ł��B
�@���ɕ����^�o�R�ɂ��Ăł��B�Q���S���ɕ��ꂽ��R�Q��r��搢�_�����Łu���퐶���̒��Ŗ��f�s���Ɗ����邱�Ɓv�̐ݖ�Ƀ^�o�R�̃|�C�̂Ă�����^�o�R�����ʁA�S�V���ł��B�����̉͂V�O�O�x�Ƒ�ϊ댯�ŁA�������͎q�ǂ��E�D�w�ȂǂɈ��e���ł��B���͂ɕs������^���Ă��邾���ł͂Ȃ��}�i�[������܂��B�u���������~�߂悤�L�����y�[���v������Ɍ��ʂ��オ��悤�ɋ������邱�Ƃ����߂܂��B���������������B
�@�Ō�ɍH�Ɨp���ɂ��Ăł��B
�@�����s�̍H�Ɨp�����Ƃ��p�~�ɂȂ�H�ƐS�z�̐����o�Ă��܂��B�H�Ɨp�������Ƃ́A���Ɨp���̒n�����ݏグ�ɂ��n�Ւ����h�~����A���ƎҎx���Ƃ��Ďn�܂�A���̌�A�s���ĊJ�����ƂŌ��݂��������n��̏Z����̎{�݂ł��g�C���p���Ɏg���Ă��܂��B���ʂ̐��������g�����i�i�Ɋ����Ő����オ��U���̂P���x�ōς݂܂��B�p�~�ƂȂ�Δz�ǂ̐ؑ֔�p�␅����l�グ�ɂȂ�ƕs����������Ă��܂��B���ɔ�颐��n��œ����s���U�����Ă����̂Ƃ��āA�ӔC�������Čp�����邱�ƁA����A���ƕύX�ȂǂƂȂ�ΕK�v�ȑ��s�����{����悤��Ƃ��ē��������邱�Ƃ����߂܂��B
�@����ő�P��ڂ̎�����I���܂��B
�s���فt
�y�����|�������فz
�@�n�����g�����̑�Ƃ��āA�u����̂b�n�Q�팸�ڕW�v�Ɋւ��鎿��ɂ������������܂��B
�@��ł́A����i�s�s��ڎw���āA�n�����g����ɂ��ϋɓI�Ɏ��g��ł���Ƃ���ł������܂��B
�@�������r�o�����b�n�Q�̍팸�Ɍ����āA�斯�⎖�Ǝ҂ւ̊��u�������J�Â��Ĉӎ��[�����s���ق��A���z�����d���u�≮��Ή��Ȃǂ�ݒu�������̏Z��⎖�Ə��ɑ��āA�ݒu��p�̈ꕔ����������u�G�R�������x�v�����{���A�b�n�Q���̊����ׂ����炷�ݔ��̕��y��}���Ă���܂��B
�@��̎{�݂ɂ����܂��Ă��ԗ��̃n�C�u���b�h����A���w�Z�ւ̔R���d�r���u�̓����A�k���ɂł̒��ԏ�̎Ő����ȂǁA���z���ݔ��𗦐擱�����Ă܂���܂����B�r���������z������s���v��ł́A�{���ɂł̂b�n�Q���̔r�o�ʂ��A�m���ɍ팸���Ă���A���ʂ������Ă���܂��B
�@�V�N�x�ɗ\������Ă���u�r�������v�̐���ߒ��ɂ����āA����̂b�n�Q�팸�ڕW��v����܂���悤�A�������Ă܂���܂��B
�y�����|�������فz
�@����̑�C���������Ɖ��P�v��ɂ��Ă̂�����ɂ������������܂��B
�@����̑�C�������́A�����s������̒B����c�����邽�߁A��ʊ���C����ǂ��Z�������w�Z����ɐݒu���āA��_�������A��_���Y�f�A���V���q���A��_�����f�A�����w�I�L�V�_���g�A�C�ۂȂǂɂ��ď펞������s���Ă��܂��B�\���N�x�̌��ʂ́A�����w�I�L�V�_���g�Z�x�����������B�����܂����B�܂��A��Ǝ��ɂ́A���V������y�ы��������������A�_���J�����A�����̎R�⌚���Ȃǂ�ڕW�ƂȂ���̂ږڂŌ��āA���̌������ő�C���ׂ钭�]�������s���Ă��܂��B
�@���ɑ�C�����̉��P�v��ɂ��Ăł������܂����A���݂̉��������́A��Ɏ����Ԃ̔r�o�K�X�ɂ����̂ł���A��C�����h�~���i�߂邽�߁A�r������{�v��Ɋ�Â��A�u�����ԗ��p�̗}���v�u����Q�Ԃ̓������i�v�Ȃǂ����{���Ă܂���܂����B
�@����ɁA��ł͓��퐶���ł̈ړ���i�����̑��ʂ��猩�����N���}�ɗ���߂��Ȃ���炵�����邱�ƂŁA������ʂ̗��p�𑝂₵�����Ċy�����܂������邱�Ƃɂ��A�b�n�Q�̍팸��}�����ʐ���Ɏ��g��ł܂���܂��B����́A�r���ɂ�����^�A����ł̂b�n�Q�r�o�ʂ��A������\�N�A��\��N�ɂ����Ă��ꂼ��ΑO�N���p�[�Z���g�팸������g�݂ł������܂��B
�@��Ƃ������܂��ẮA�������C���̔c���Ɗ��ۑS�ɉs�ӎ��g��ł܂���܂��B
�y�����|�������فz
�@���������h�~�L�����y�[���̎��{�ɂ��Ă̂�����ɂ������������܂��B
�@���������́A�z���k�̃|�C�̂ĂŊX����������A�����̂����̉Ύ�́A�ʍs�l�̑����w�t�߂ł́A��ϊ댯�ȍs�ׂł���ƔF�����Ă���܂��B
�@��ł́A�u�r���܂��̊��������v�����N�ɐ��肵�A��Ƌ斯�����͂��āA�������������H���A�����Ŕ������܂������邱�Ƃ�ڎw���Ă��܂��B
�@���݂̕��������h�~�L�����y�[���ɂ��܂��ẮA���N�܌��`�Z�����d�_�I�ɋ���̎�v�e�w�O�ɂ����āA�斯�̕��X�̂��Q�������������āA�L�����y�[�������{���Ă���܂��B
�@�܂��A���f��������_�t�߂ɘH�ʃX�e�b�J�[��\������Ȃǂ̑���u����ƂƂ��ɁA�H�ʃX�e�b�J�[�̕\���ӏ���N�X���݂��Ă���܂��B
�@������A�������r����ڎw���āA�ϋɓI�Ȍ[��������l�X�Ȋp�x���猟�����Ă܂���܂��B
�y������敔�����فz
�@�H�Ɨp���Ɋւ���䎿��ɂ��Ă��������܂��B
�@�����s�̍H�Ɨp�������Ƃ́A�n�Ւ�����Ƃ��āA�n�����g���K���̑�����������邽�߁A���a�O�\��N�ɍr�����܂ލ]���n��ŊJ�n����܂����B
�@���݂̍H�Ɨp���̗��p�́A���a�l�\��N�x�̃s�[�N���ƕ����\���N�x���ׂ�ƁA��{���ʂ͎O�\�ܖ�?����O��?�Ə\���̈�ȉ��ɁA�_���͘Z�S��\�܌������S�l�\�����Ɣ����ȉ��ɂ��ꂼ��啝�ɗ�������ł���A�r�����ōH�Ɨp���𗘗p���Ă��鎖�Ǝғ��̌_���͎l�\�����x�ƕ����Ă���܂��B
�@�����s�́A����A�H�Ɨp����������I�ɋ������邽�߂ɂ́A�V���������{�݂̉��C���K�v�ƂȂ邪�A��K�͂Ȏ{�ݍX�V��p�Ɍ����������̎��v�������߂Ȃ��������ɂ��邱�Ƃ���A�p�~���܂߂��������s���ƕ����Ă���܂��B
�@��Ƃ������܂��ẮA�����s�̓����𒍎����A�����Ƃւ̉e�������l�����A��Ƃ��Ă̑Ή����l���Ă܂���܂��B
���y�[�W�g�b�v
|